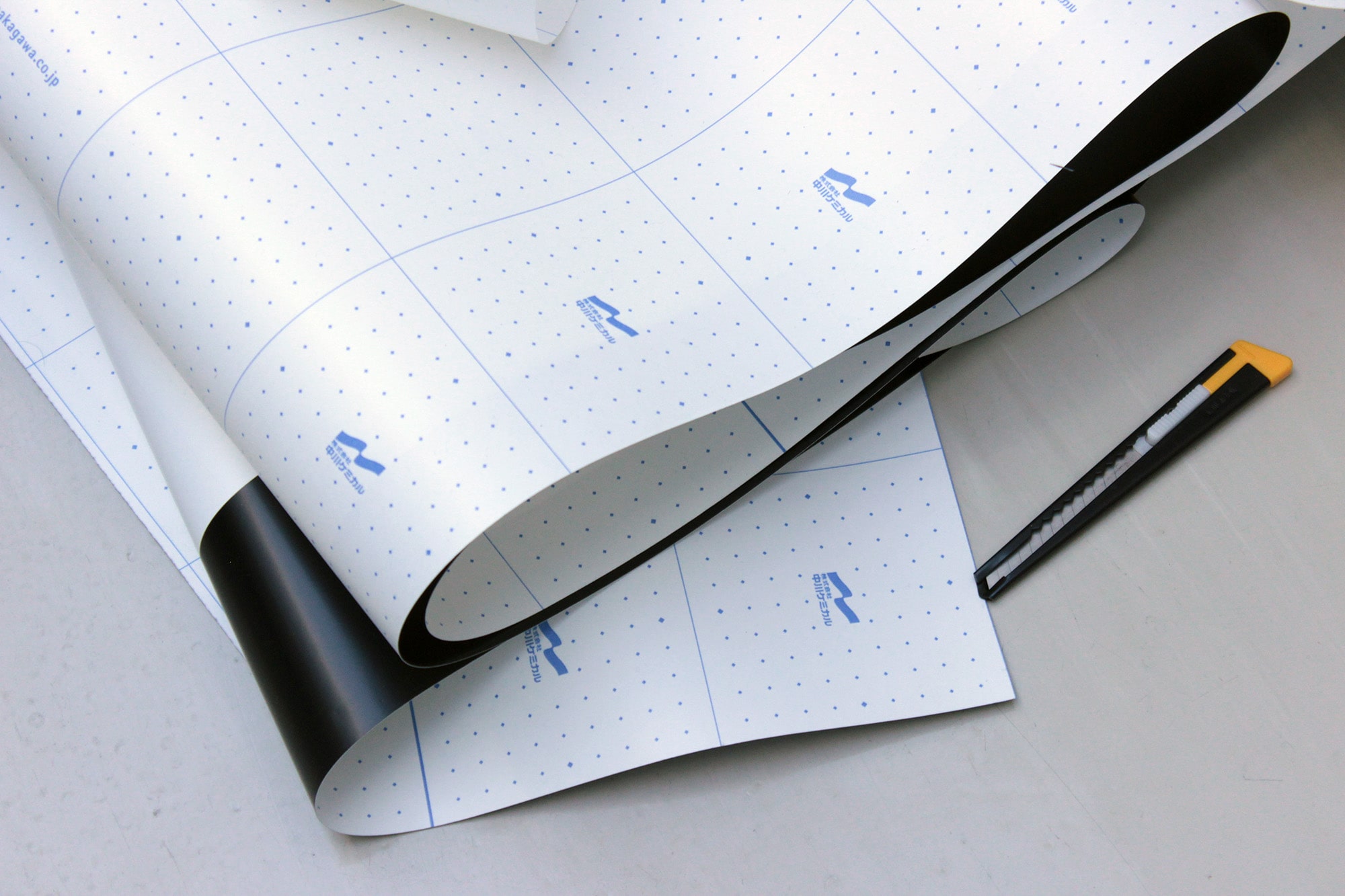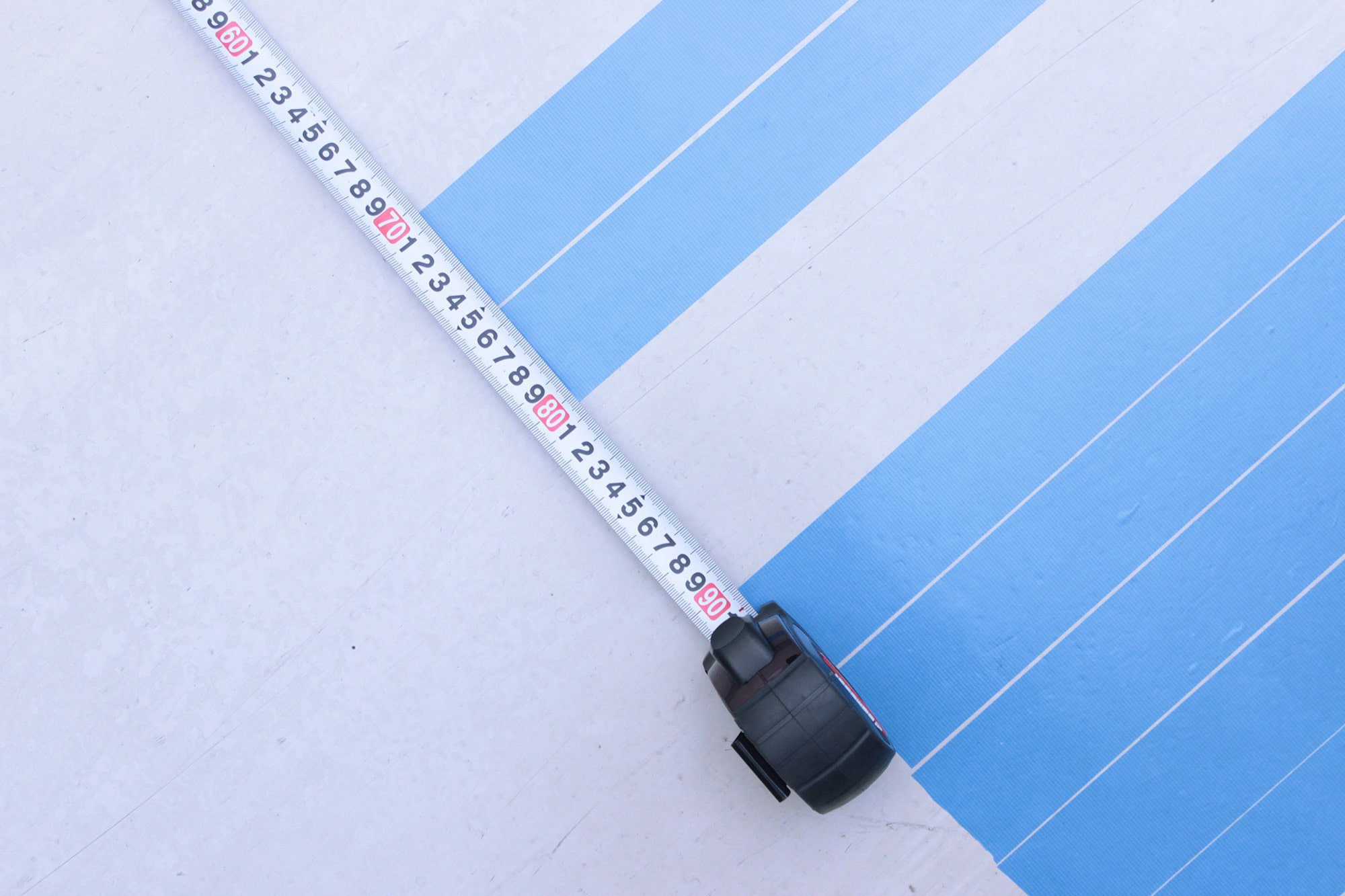2020年度 優秀賞&同窓会特別賞
無縁仏と縁を紡ぐ
──小さな記録と微かな記憶を辿る私的なドキュメント──
- 米山 友葵さん
📝要旨📝
どんなに忘れたくないことがあったとしても、時の流れやそれに伴う遺却に逆らうことはできない。どんなに祈り、悔やみ泣いても、死者には会うことができない。取り戻したい「過去」があったとしても、もう一度会いたい人がいたとしても、わたしたちには過去に戻る術がない。しかし「過去に触れる」ことはできる。
筆者の実家敷地内には複数の無縁仏が存在する。それらは、国替え及び参勤交代の際に道中行き倒れになった者を先祖が祀ったものだと祖母は言う。無縁仏とは一般に、継承者がおらず供養者不在の墓のことである。よく知られているのは、災害や戦争などで多くの命が失われた際に埋葬を行うことができなかった者の供養を目的として建てられる供養塔ではないだろうか。公地に建てられ、各地域にある寺や自治体が管理することが一般的である無縁仏が、何故一般家庭である我が家の敷地内にあるのだろうか。本研究はまずこの問いから出発した。しかし、あらかじめ結論を述べておくならば、筆者が行った調査によって、実家にある無縁仏の史実を明らかにすることはできなかった。墓石の下に眠る人物の名前、齢、この場所で弔われるに至った経緯、それらは筆者の手の届く範囲の資料では知ることができなかったのである。しかしながら、客観的な史実を実証的に明らかにすることはできなかったものの、筆者は無縁仏に纏わる調査の過程で多くの「過去の気配」を感じたのである。埃を纏った本を手に取った時に感じた重み、「過去に触れ」損うことで齎された新たな過去との邂逅、亡き祖父が遺した肉筆の記録、墓石の肌理に遺る身体の記憶…それらを自身の身体で感受し、書きあらわす行為は、いわば「過去に触れる」とでも言いうる経験であった。
田中純は、著書『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス──』(羽鳥書店、2016年)の中で、歴史的な過去と個人の記憶が入り混じり合う様子や、嗅覚や触覚といった個人の身体感覚に則した経験的な歴史との関わりのことを度々、「過去に触れる」と形容している。論理的でなく、客観的事実とはし難い現象であるが、「触れる」という肉体的で、やや官能的なイメージを持つ言葉でしか言い表すことのできない経験をすることが確かにある。「過去に触れる」とは、そのような経験によってのみ生まれる、対象を知らないままで縁を結ぶこと、いわば無縁なものの有縁化の謂いである。そのことを踏まえ本論は、筆者の実家に無縁仏があることの理由を問うことを端緒として生じた「過去に触れる」という経験について、田中純の著書『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス──』及び、カルロ・ギンズブルグ(Carlo Ginzburg,1939-)が著書『チーズとうじ虫』(杉山光信訳、みすず書房、1984年)に記した、拓かれた公的な歴史を辿るだけではなく、目を向けずに生きてゆくことが容易いほどにありふれた存在や、微かな気配を感じ取り、それらを書き表し、時には「再生」するという行為を手本として、叶う限り仔細に記述することを目的とする。すなわち、無縁仏に纏わる「縁」について詳細に物語ることで、身体的な感覚に則した歴史の在り方について考えることが本論の目的である。それゆえ本論文は、研究の結果を史実に基づき客観的かつ論理的にまとめるのではなく、筆者個人が文字通り肌で感じたことの主観を仔細に記述するという体裁を採用する。いわば本論は調査を通じて「過去に触れ」てきた筆者の私的ドキュメントである。
第一章では、筆者が無縁仏の史実を明らかにしようと調査を進める過程において、研究により明かされた結果のみが客観的な史実として新たに記録されるという、所謂「歴史」の在り方に疑念を抱き、歴史を紡ぐという営みそのものについて考えることで、私的で小さな記録の存在に気づくまでの過程を記述する。続く第二章では、小さな記録に纏わりついたえも言えぬ気配を肌で感じ、今は亡き者が過去に記した記録や、忘れられた記憶に触れようと試みることを通じて、筆者が記録に宿る記憶の気配と、その「再生」について考える過程を記述する。第三章では、血縁をあらわした家系図や、今は亡き人物が過去に行った行動を筆者自身の身体で「なぞる」ことで、記録を通して死者との邂逅を果たすまでの過程を記述する。おわりにでは、小さな過去に目を向け、不在に声に耳を澄ませ、記憶の気配を感じ、それらの過去を結び、時には絡まり、結んだはずのものが解けてしまうその様子までをも、共有可能な形で表出するというこの行為がまさに縁を紡ぐ行為であり、それもまた、ひとつの「歴史」の在り方であると結論づける。
歴史学的な過去の認識方法が最も一般的で確かなものであるとされる中でも、わたしたちは、客観的に見れば単なる四角い大きな石であるはずの墓石の前に身を屈め、花や食べ物を供え、両の掌を合わせ、そこにあるはずのない故人の姿を追想する。実のところわたしたちは日常的に、墓石という無機質なものを憑代として、記憶という曖昧なものを頼りに、極めて身体的かつ呪術的な方法で「過去」を認識しているのだ。
わたしたちは常に死と背中を合わせて生きている。それがわかっているからこそ、何かを遺し、遺されたものが歴史を成す。先祖が遺した無縁仏によって結ばれた様々な「縁」。これは小さな記録と微かな記憶、そして不在への「想い」が紡いだひとつの、歴史の欠片である。