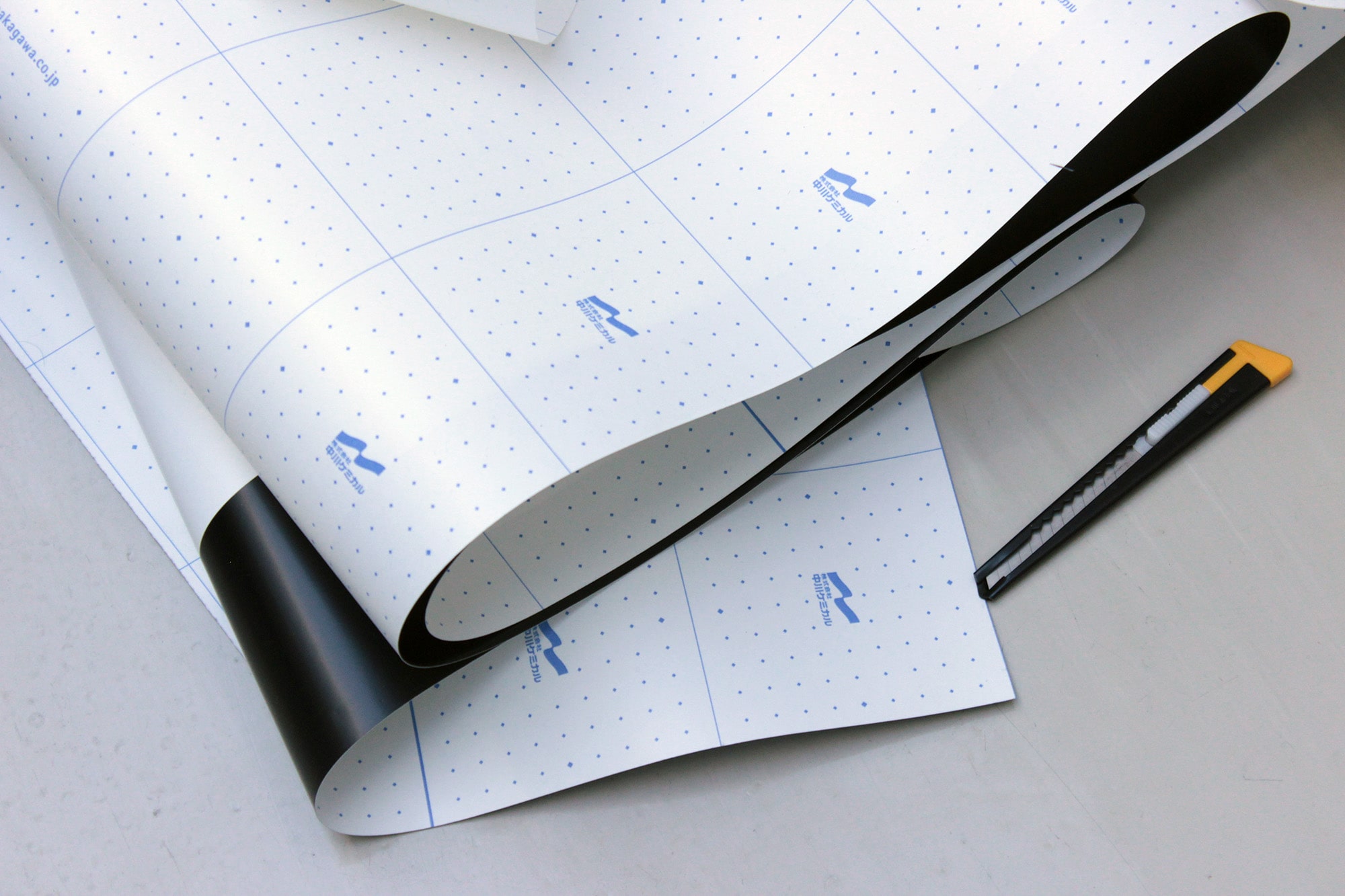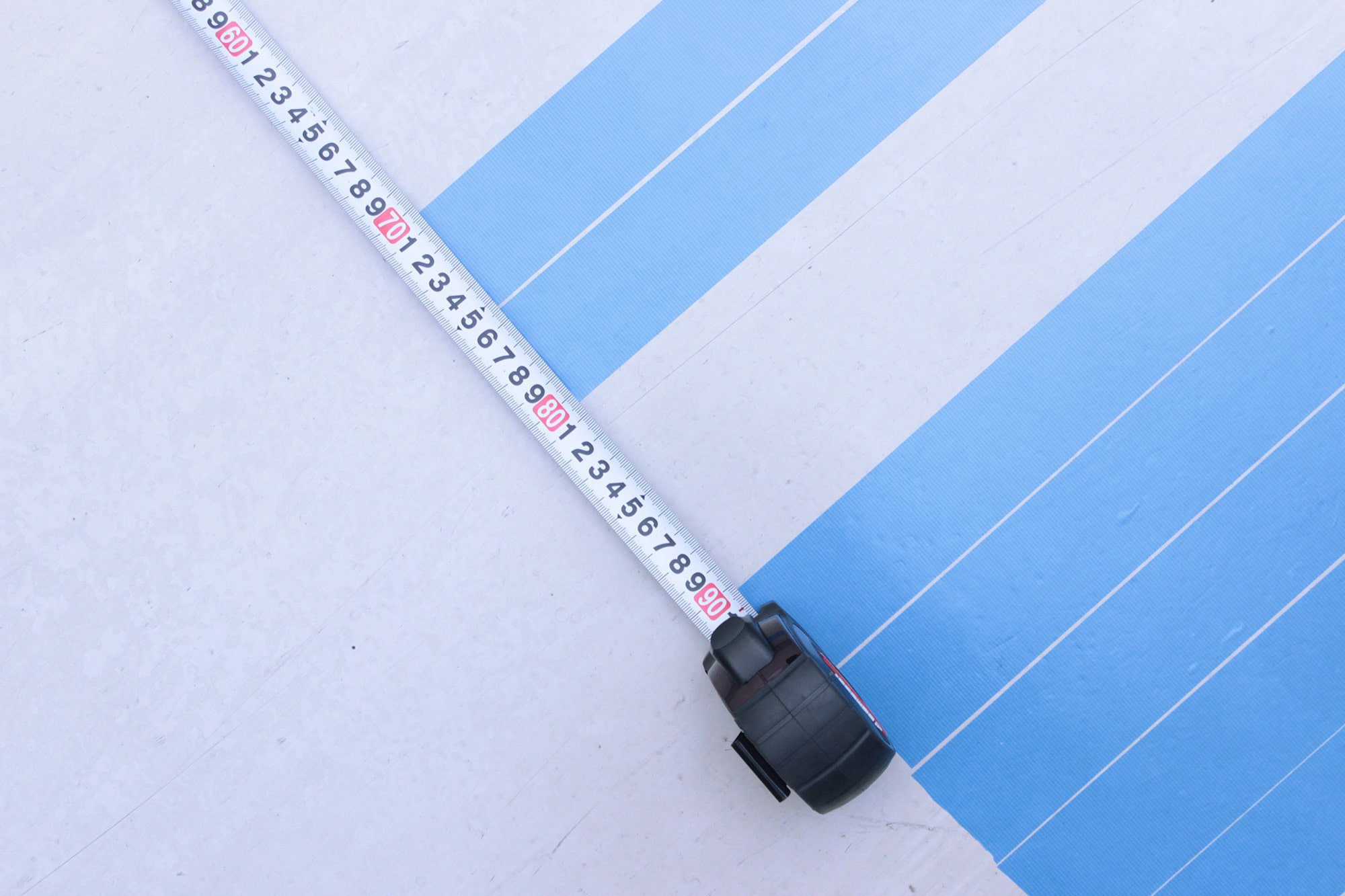2019年度 学長賞
地を這うバレリーナ
──バレエ史からみる『ジゼル』(マッツ・エック演出、1982年)の身体性──
- 森川 美里さん
📝要旨📝
『ジゼル』とは1841年パリ・オペラ座で初演されたバレエ作品である。病弱だが明るい村娘ジゼルが恋人に裏切られたショックで錯乱し、息絶え亡霊となってしまうという悲劇だ。今日、演じられる『ジゼル』はマリウス・プティパ(Marius Petipa、1818-1910)が1884年振付改訂を行ったものを範としている。数多くのバレエ作品が、歴史の中で何度も生まれ変わる中で、マリウス・プティパ版『ジゼル』は、初演とほとんど変わらない状態で現代まで踊り継がれている作品のひとつである。そうした中、異色の振付家として名を馳せるマッツ・エック(Mats Ek,1945-)が、1982年に『ジゼル』の改訂を行った。マッツ・エックの『ジゼル』は従来のそれとは全くことなった解釈を行っており、賛否両論をよんだものの、28ヶ国300回以上も世界中で上演されている。
『ジゼル』について、バレエ評論家であるシリル・ボーモントは著書『ジゼルという名のバレエ』(佐藤和哉訳、新書館、1992年)において、とりわけロシア出身の振付家であるニコライ・セルゲーエフが1884年に振付を行ったものを取り上げ、ロマンティック・バレエ時代の最高峰であると述べている。さらに「(ジゼルは)主題、背景、音楽それに振付すべてはロマン主義時代のもので、この時代を典型的に表す作品である。これを現代風にしたり、(中略)ほかの時代に移しかえようとしても、悲惨な結果しか生まれないだろう」と『ジゼル』の改訂を行うことの困難さを指摘している。ボーモントはプティパが行った振付改訂について、セルゲーエフ版に準じた一つとみなしており積極的に言及はしていないものの、鈴木晶は著書『バレエ誕生』(新書館、2002年)においてプティパの振付を重要な改訂として捉えている。というのも、プティパは、それまでのロマンティック・バレエの物語や振付を基礎としつつも、そこにプティパ自身が確立したクラシック・バレエの様式を振付に導入しており、その様式は舞踊家タマラ・カルサーヴィナ(Tamara Platonovna Karsavina、1885-1987)が「ステップひとつでも勝手に変えてはいけない聖なるバレエ」と評するほど画期的であったからである。その後もプティパの改訂は長いことそのまま継承され、今日に至るまで多くの振付家によって踏襲される規範となっている。こうしたマリウス・プティパ版『ジゼル』の物語や振付、舞台装置、衣装などを根本から変えてしまったのがマッツ・エックなのである。
本論の目的は2つある。第一に、マッツ・エックがマリウス・プティパ版『ジゼル』をどのように改訂したのかを考察すること、第二にその改訂にどのような意義があるのかをバレエの歴史に位置づけることで明らかにすることである。
この問いを明らかにするために、以下の手続きを取る。
まず、マッツ・エックの改訂がいかに大胆であったかを明らかにするため、バレエ史の中で『ジゼル』の規範とされているマリウス・プティパ版を比較対象とし、第一章と第二章でそれぞれの物語と振付を中心に作品分析を行う。第一章では、2009年オランダ国立バレエ団により上演されたマリウス・プティパ版『ジゼル』において、病弱で可憐なジゼルが死ぬことで完成する超自然的な存在を軸とした物語が、重力を感じさせない軽やかな振付によって演じられていることを明らかにする。第二章では、1987年にクルベリバレエ団が上演したマッツ・エック版『ジゼル』を取り上げ、マリウス・プティパ版『ジゼル』において失恋によって命を落としていたジゼルが、死ぬことなく精神病院に送られるという改訂が行われていること、軽やかな振付を施されていたものが肉体の重みを感じさせる力強い振付へと改訂されていることを明らかにする。第三章では、マッツ・エック版『ジゼル』を歴史的に位置づけるべく、バレエ史を概観する。ロマン主義が流行したことにより超自然的な物語が重視されるロマンティック・バレエが誕生した後、より重力からの解放を目指したクラシック・バレエが世界中で流行する。そして、現在上演されるほとんどのバレエがクラシックの形式であること、そして近年クラシック・バレエに対抗するようなコンテンポラリーダンスが勢いを増していることを明らかにする。続く第四章では、マリウス・プティパ版『ジゼル』が、死によって完成されるというロマン主義を色濃く反映したロマンティック・バレエの物語に、軽やかで重力を感じさせないというクラシック・バレエの振付を導入していること、ジゼルという娘は物語と振付の双方において重力から解き放たれ人間的身体を超越した精神的存在へと昇華していること、だからこそ今日においてマリウス・プティパ版『ジゼル』は規範となり、バレエの理想を体現したバレエ史上最も重要な改訂のひとつとなっていることを明らかにする。それに対してマッツ・エック版『ジゼル』は、死ぬことなく精神病院へ送られる反ロマン主義的な物語と人間的身体の重みを感じるコンテンポラリーダンスの振付へと改訂していることを確認する。そのことを踏まえ、マッツ・エック版『ジゼル』が、バレエの理想とされていた超越的な身体とそれを内容的に補強する物語を否定するかのように、ジゼルを精神的存在から肉体的・人間的存在へと引きずり降ろした反ロマンティック・バレエ且つ反クラシック・バレエであることを明らかにする。
終章では、マッツ・エックの改訂が、女性の死をもって完成するというロマン主義的な物語への挑戦であり、したがってそれを理想とするバレエそのものへの批判であると結論付ける。ボーモントはロマン主義の典型としての『ジゼル』を理想としていた。しかし、ジゼルの死によって完成される理想という主張こそが悲惨なのではないか。その意味において、反バレエ的なマッツ・エック版『ジゼル』は、ボーモントが指摘した改訂の困難さを見事に克服しているのである。