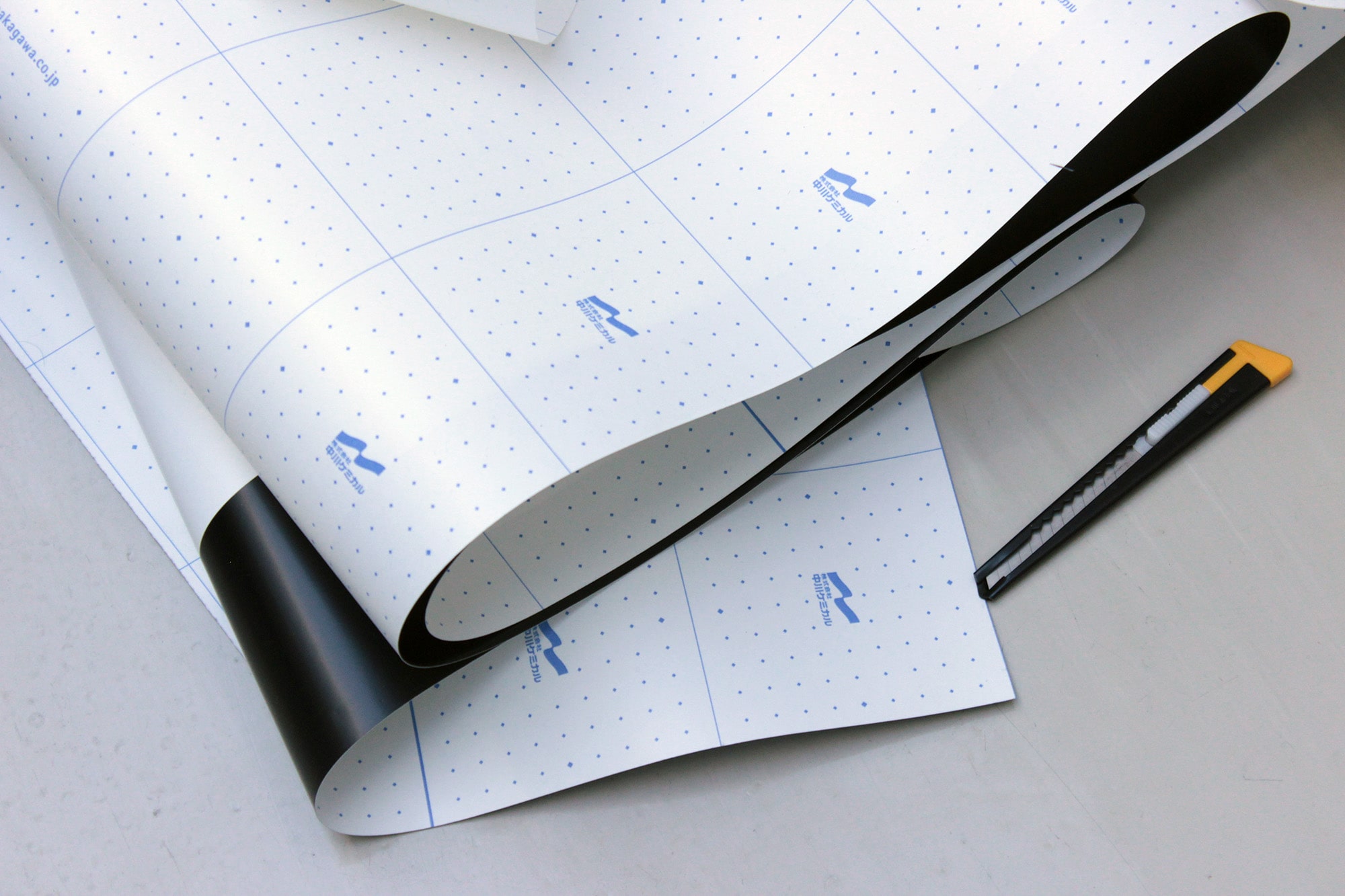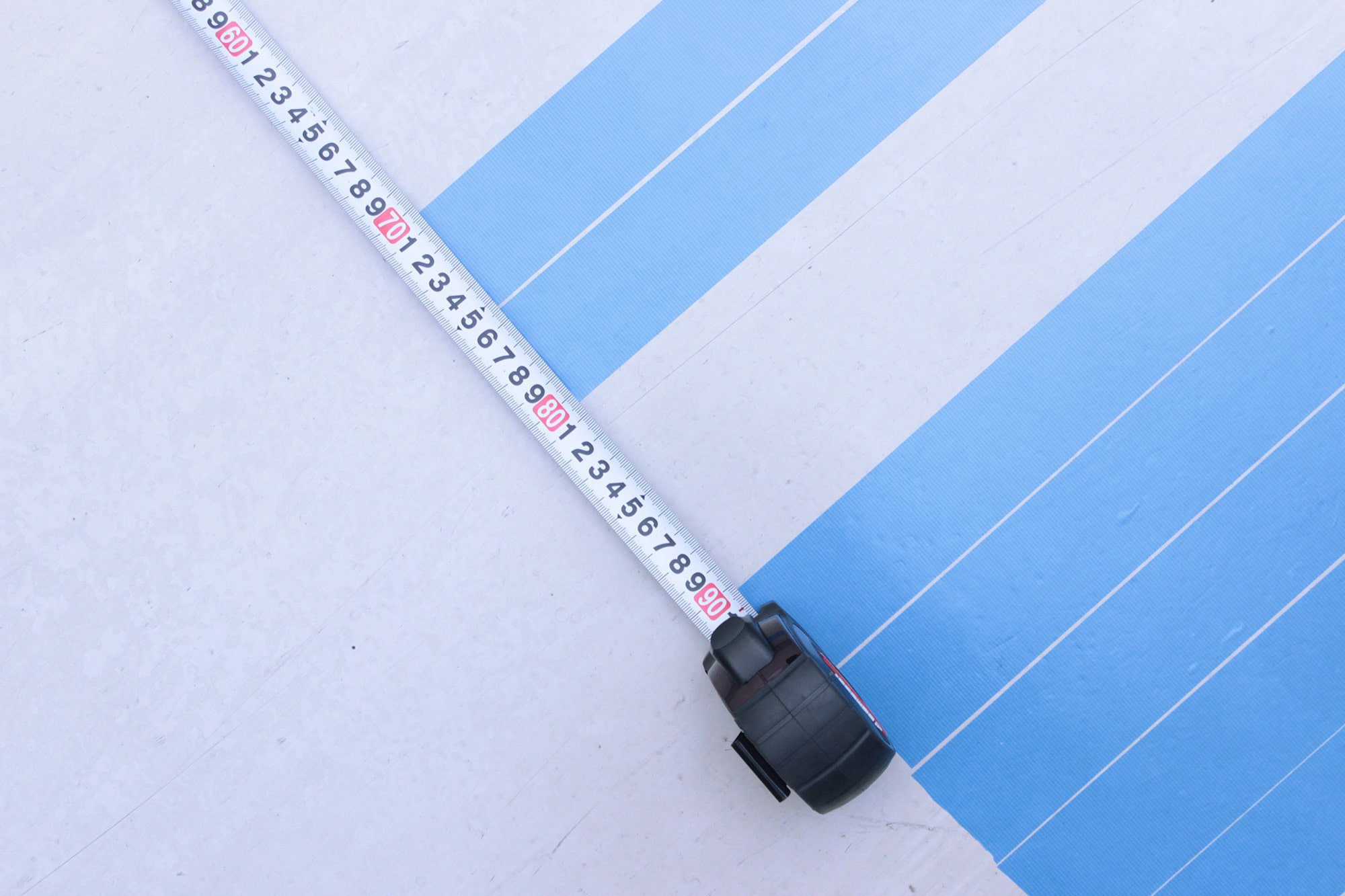2019年度 優秀賞
「境界」を失ったミュージアム
──「儀礼」という観点からみる観賞の場──
- 屋宜 初音さん
📝要旨📝
ミュージアムと聞くと、どのような空間をイメージするだろうか。荘厳な外観、厳めしい彫刻が置かれ、入場するのさえ緊張してしまうような入り口。展示室には傑作と呼ばれる作品が並び、その横には難解なキャプションが添えられる。展示室内はとても静かで、教養のある人、美術が分かる人以外はとてもじゃないが楽しめない、といった具合だろうか。こうした閉鎖的で限られた人にしか楽しむことのできないミュージアムというイメージは、18世紀以降の近代に作られた国立のミュージアムを拠り所としている。ルーヴルをはじめとする国立のミュージアムの多くは、かつて権力を握っていた王侯貴族のコレクションをもとにしている。そのため展示作品、展示の内容にはエリートたちの教養・思想・価値観が反映されていたのだ。ミュージアムは一般市民が入りづらい、敷居の高い空間であると思われるのも無理はない。このような一部の人による価値観を観客に押し付けるミュージアムの構造を、美術史家のダンカン・キャメロンは「神殿」と称した。
「神殿」としてのミュージアムは、観客にとってどのような空間だったのだろうか。美術史家のキャロル・ダンカンはこの問題に取り組んだ研究者の一人だ。彼女は著書『美術館という幻想 儀礼と権力』(川口幸也訳、水声社、2011年)において文化人類学の概念を応用し、「儀礼」という観点からミュージアムでの観賞体験を分析した。ミュージアムは厳格な観賞の作法や荘厳な建築によって日常生活の空間からその空間を分離し、展覧会を通して観客に変容を促していると言う。非日常を通過することによって人を変容させる構造は「儀礼」のもつそれと一致しているとし、「儀礼」によってミュージアムは権力と結びつき、近代において国家の啓蒙装置として機能していたと述べる。近代のミュージアムとは、ある思想に沿って観客を変化させる「儀礼としてのミュージアム」なのだ。近代のミュージアムは表向きには公衆に開かれた空間としながらも、実際は限られた観客にしか喜びを与えない観賞の場であった。
しかし1970年、一部の人にしか奉仕しないミュージアムを批判する抗議活動が欧米で勃発する。閉鎖的なミュージアムに、ついに変革の時が訪れたのだ。ダンカン・キャメロンはミュージアムが生き残るために、誰もが参加・利用できる「フォーラム」をつくる必要があると提言した。これ以降ミュージアムはより多くの人のために、開かれた観賞の場になる努力を惜しまない。たとえば展覧会を解説するツアーをおこない、レストランやショップを館内に取り込んだ。国内のミュージアムも例外ではない。「教育普及」という言葉が積極的に使われるようになり、市民が利用できる実習室やアトリエをミュージアム内に設け、地元の作家を講師に招いた実技講習会や展示室講話などが盛んにおこなわれている。また、「子ども」「親子」「障害者」など、それまでのミュージアムが対象としてこなかった人たちに光を当てる企画が多く開催されるようになった。たとえば、国立国際美術館では「こどもびじゅつあー」と題した幼児向けの観賞プログラムや、小中高校と連携したスクールプログラムをおこなっている。他にも金沢21世紀美術館は、ミュージアムの床を、段差のないバリアフリーにすることで誰もが利用しやすい空間をつくりだした。せんだいメディアテークは独自のコレクションよりも地域連携のプロジェクトを重視し、コミュニティセンターのような役割を果たしている。1970年代の抗議活動から40年という短い期間のなかで、かつて「神殿」であったミュージアムは誰にでも開かれた「フォーラム」へと急速な変化を遂げつつある。
「フォーラム」化したミュージアムは観客にとってどのような空間だろうか。敷居を下げ誰でも気軽に訪れることができる現代のミュージアムは、キャロル・ダンカンが「神殿」としてのミュージアムに見出したような、観客を変容させる儀礼構造を受け継いでいるのだろうか。またどのような構造を設け、観客に何をもたらしているのだろうか。
本論ではダンカンの「儀礼としてのミュージアム」という考え方をもとに、「フォーラム」化したミュージアムが観客にとってどのような観賞の場であるのかを明らかにする。そのために以下の手続きを取る。 第1章ではミュージアムが閉鎖的な空間から解放的な空間へと変化したことを、歴史的文脈に沿って整理する。ダンカン・F・キャメロンの論考「美術館―神殿かフォーラムか」(高島平吾訳、『あいだ』99号、桂書房、2004年)を参照し、18世紀に誕生したミュージアムは約300年の時を経て、国の啓蒙装置としての「神殿」から、誰もが気軽に利用できる「フォーラム」へ変化したと結論付ける。第2章ではキャロル・ダンカンの議論を参考に、ミュージアムがもつ儀礼構造を明らかにする。まず人類学における儀礼の概念と構造の特徴を参照し、ミュージアムの儀礼が成立するには、①観賞作法や建築によって日常から自らを分離し非日常且つ神聖な空間を生み出すこと、②展示によって観客に物語を演じさせること、が不可欠であることを確認する。そして近代のミュージアムはこうした儀礼構造によって観客に変容をもたらしていたと結論付ける。第3章では「フォーラム」化したミュージアムの事例として金沢21世紀美術館に焦点をあて、そこには儀礼構造が引き継がれているのか、またそのような構造を設け観客になにをもたらしているのか分析・考察をおこなう。金沢21世紀美術館は、境界を生まない建築や、観賞作法の緩和によって日常と地続きの空間を生み出そうとしていること、観賞順路を指定しないことより観客に物語を強制しないことを明らかにし、「フォーラム」化したミュージアムには儀礼構造が存在していないと指摘する。そして境界を失ったミュージアムは、誰もが楽しめる開放的な観賞の場を手に入れた代わりに、観客が変容する機会を失ったと結論付ける。終章では2019年にあいちトリエンナーレにて開催された「表現の不自由展・その後」を取り上げ、入場制限や時間制限といったなんらかの制限を設けることにより、「フォーラム」化したミュージアムでも儀礼構造を構築することが可能だと述べる。