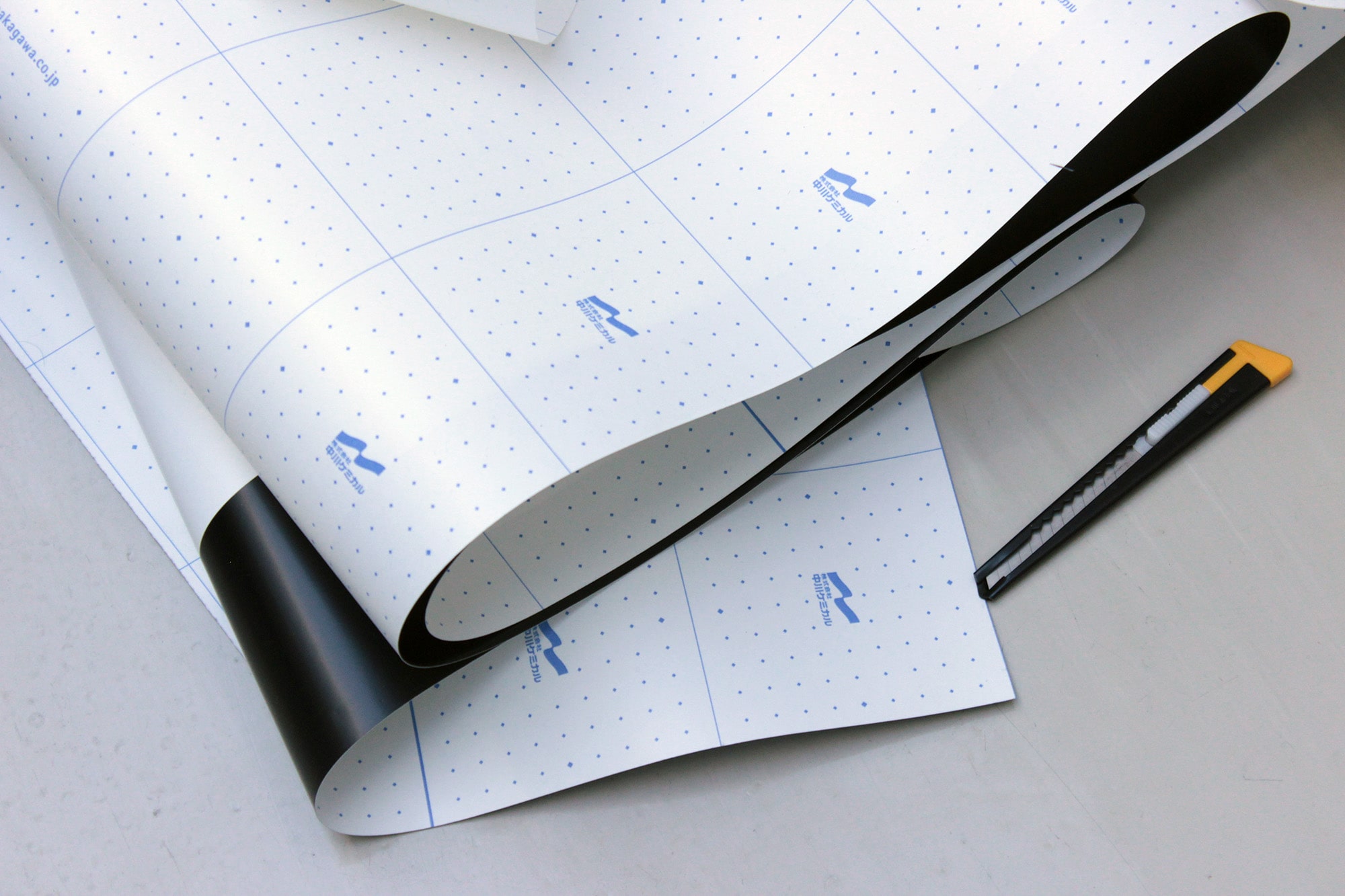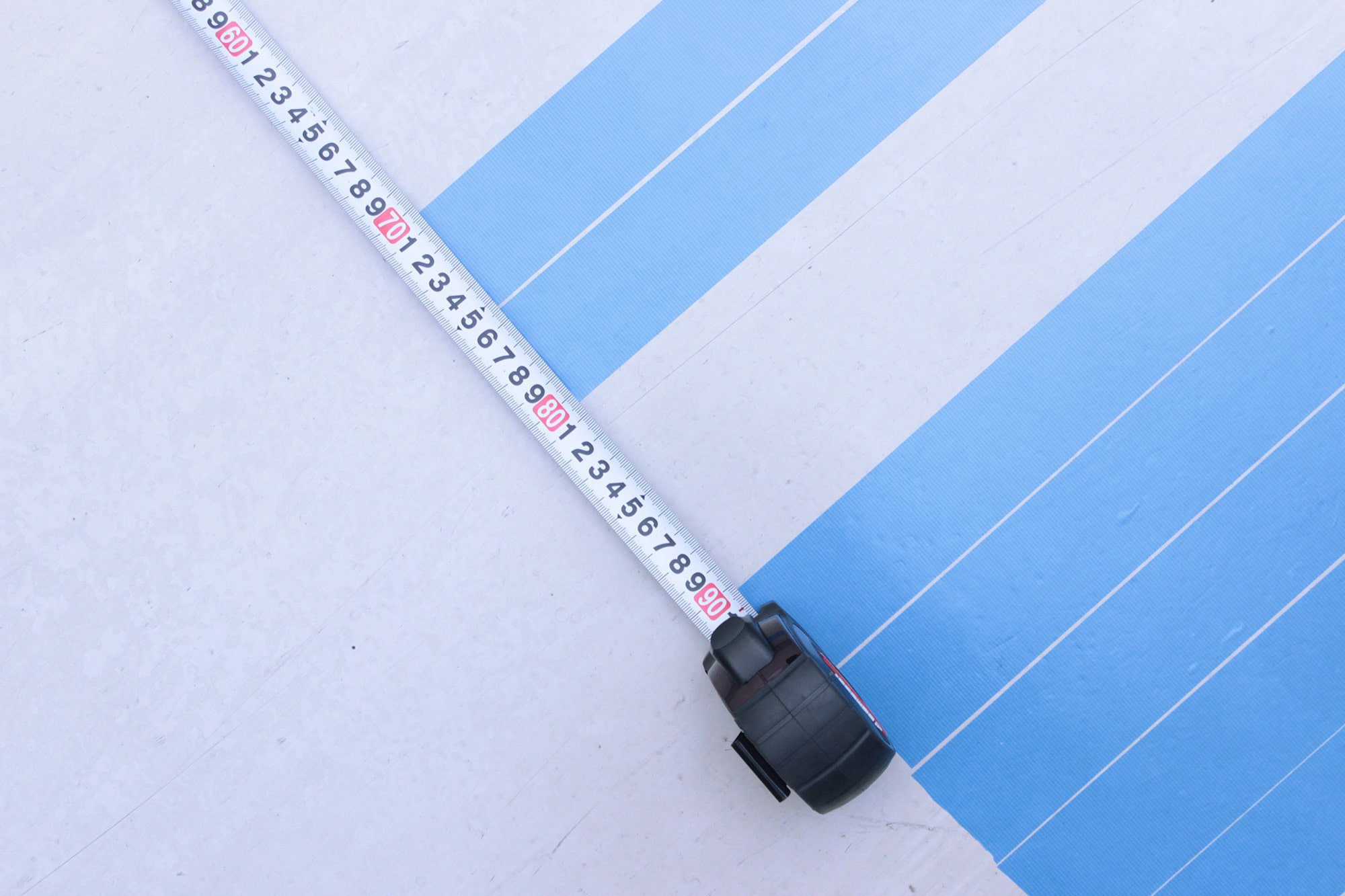2016年度 奨励賞
日本製ディズニーランド/妖精の死をこえて
- 上野 綾香さん
📝要旨📝
“夢と魔法の王国”
“地上で一番幸せな場所”
“すべてのアメリカ少年の故郷”……
世界的テーマパークであるディズニーランドには、様々な呼び名がある。ウォルト・ディズニー(Walter Elias Disney,1901〜1966)によって創られたアメリカ生まれのこの“国”は、いまや世界中に点在し、他のテーマパークとは一線を画す人気ぶりを誇っている。その魅力は、テーマパーク全体をひとつの“国”と言わしめるほどの、統一された世界観である。空間全体が持つ〈物語〉を、パーク内のあらゆるもの—アトラクションやレストラン、ショップの内装、植わった植物から地面の色まで—が表現することにより、まるで一本の映画に入り込んだかのような、非日常的な空間を作り上げている。“夢と魔法”と銘打たれているが、その“魔法”は、人の手で異様なほどに作り込まれたものなのだ。
ところが、このように〈物語〉を軸にした空間を作って人々を誘い込み、消費を促すという手法は、近年ショッピングモールなど私たちの「日常」でも多用されている。日本のみならず世界中を覆いつつあるこの現象は、社会学者たちによって《ディズニーランド化》と名づけられた。
その一方で、日本のディズニーランドも、いまや完璧な「非日常」である、とは言い難い。アメリカの歴史やそこから生まれた冒険物語をモチーフにすることで、アメリカ人のノスタルジーに訴えかけようとしたのが、本来のディズニーランドであった。しかし、より日本人の心を掴むには、夏祭りやお正月といった、日本的なコンテンツの導入が必要であった。いまの東京ディズニーリゾートは、そうして出来上がったのだ。この現象を、有馬哲夫(1953〜)は《ディズニーランドの日本化》と呼んだ。
つまり、私たちの「日常」である商業施設や街中は《ディズニーランド化》し、夢のような「非日常」であったはずのディズニーランドは《日本化》している。現代の日本で“夢の国”を通して見えてくるのは、日常と非日常の境界が不確かになり、交わりつつある様相だ。一体、その変化の背景には何が潜むのか。本論では、〈物語〉というキーワードから、この疑問を紐解くことを試みた。
さて、非日常と日常の混在を確かめるには、まず、ディズニーランドが生み出していた非日常がいかなるものかを確かめる必要がある。ここで、空間に〈物語〉を与えるディズニーランドの手法を《物語消費》として捉えた大塚英志(1958〜)の論にふれる。《物語消費》とは、ただ単に商品を消費する行動とは異なり、ある世界観、つまり何かしらの物語が商品の背景に潜んでいるとき、消費者は物語の「断片」である商品を消費することで、世界観の全貌に迫ろうとするという行動だ。この《物語消費》を成り立たせようとするとき注意すべきなのは、物語の〈内部〉に〈外部〉を介入させないということだ。物語の内と外を指し示しているこの言葉は、「虚構」と「現実」とも言い換えられよう。
しかし、日本のパークの一部である東京ディズニーシーに対し、パーク内にいても東京都の景色、つまり「現実」が見えてしまうことへの指摘や、あるアトラクションの廃止をきっかけとした、〈物語〉の崩壊が度々話題になっている。この要因のひとつとして考えられるのは、東浩紀(1971〜)が唱えた《データベース消費》の台頭である。《データベース消費》とは、消費者が作品をただただ情報の集積として捉え、そこから好む情報のみを選びとって消費する、という行動である。作品の背景や世界観を欲することなく、単純にデータを欲する人々と、それに応えつつあるディズニーランドの姿は、新たな《日本化》の一歩だといえるだろう。
このように、ディズニーランドの〈内部〉がひらかれ、日常と非日常が混ざる様相は、現代の消費形態の変遷に沿って生まれたもののように感じられる。しかし、実はそういうわけでもない。日本の伝統芸能である歌舞伎・文楽には、〈外部〉からの介入によって物語が成り立つ場面や、〈外部〉の存在も含めて物語を楽しむ人々の姿があった。また、童話を原作とし、ディズニーアニメーションとしても人気の高い『くまのプーさん』でも、〈外部〉の存在を描いたさまざまな演出が為されている。ここから見えてきたのは、現実と虚構が区別されずとも、〈物語〉を楽しむことができるという、日本人の感性に秘められた新たな可能性であった。つまり、〈外部〉を介入させないことだけが〈内部〉を守る方法ではないということだ。
では、そもそも〈物語〉が求められなくなったのは一体なぜなのか。北田暁大(1971〜)によれば、この背景に、人々の「接続的不安」があるという。絶えずSNSをチェックし、手元の小さな箱から情報を得ることに夢中な現代人にとって、「誰にも見られていないかもしれない」という不安は何よりの恐怖なのだ。常に人と「つながる」ことに価値を見出している彼らからすれば、完全に〈外部〉を遮断した空間など、本来の欲望とは対照的なものだろう。「日常」と「非日常」の背後に潜むのは、ただ単なるディズニーランドの変容ではなく、社会における人々の欲望の変化であったのだ。
人々の欲望の変化は、ディズニーランドの〈物語〉を大きく揺るがす原因となった。ディズニーがこれまで要としてきた〈物語〉世界の崩壊を、新たな「進化」だと捉えなおしたとき、見えてくるものは何だろうか。
本論を通して浮かび上がってきたのは、人々が信じ求めなければ、たちまち消えてしまう〈物語〉の儚さだ。それでも〈物語〉を必要とする私たちを、ディズニーランドは迎え入れている。現実を見つめるだけでは生きられない切実さと、そんな切実さから創られた夢や魔法がない交ぜになるその“国”は、ウォルト・ディズニーの言葉の通り、「永遠に完成することはない」。私たちが現実を生きようとする限り、虚構は価値を持ち続ける。私たちが現実と向き合い続け、生き続ける限り、そこは“地上で一番幸せな場所”で在ろうとするのだろう。