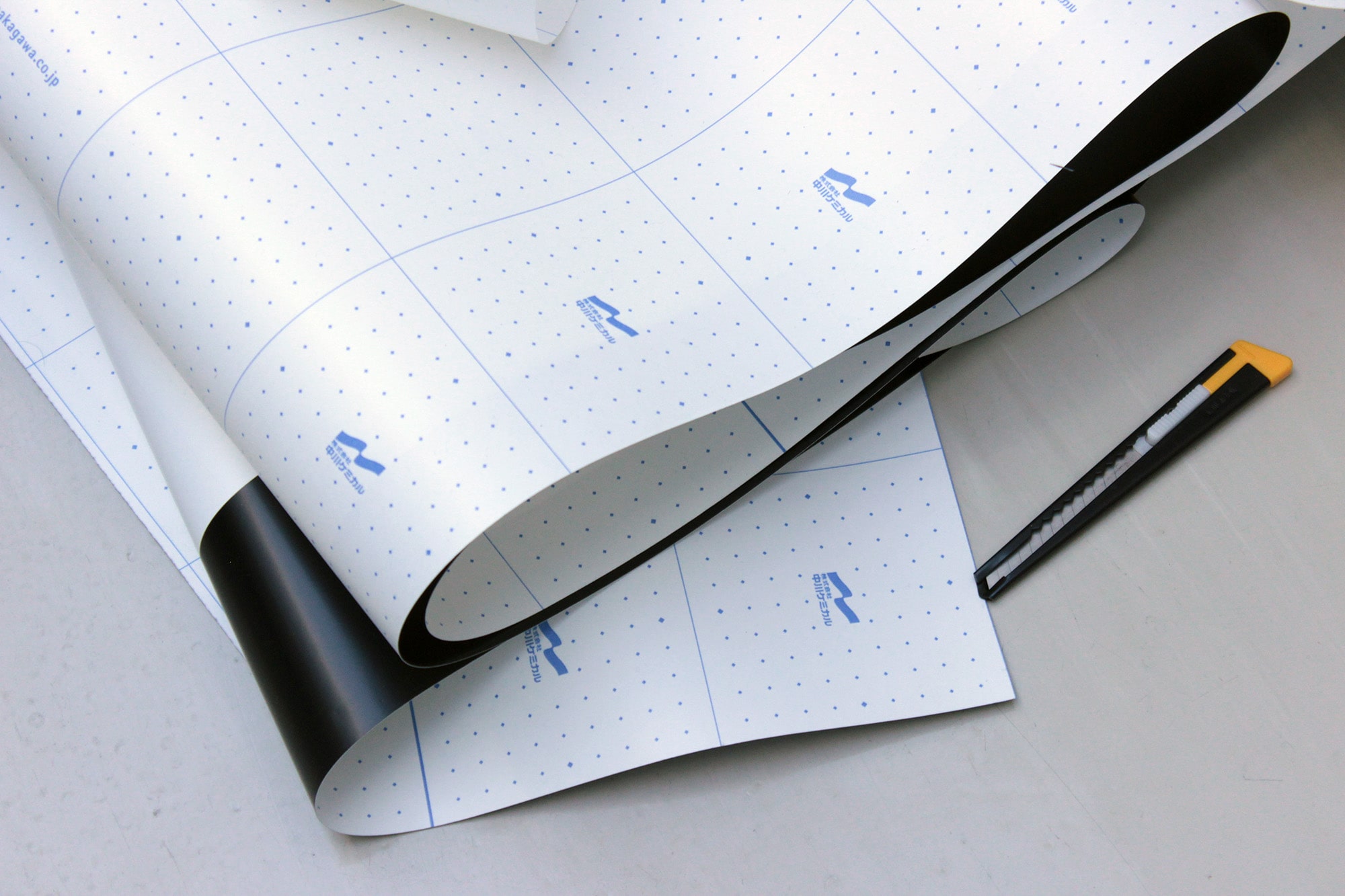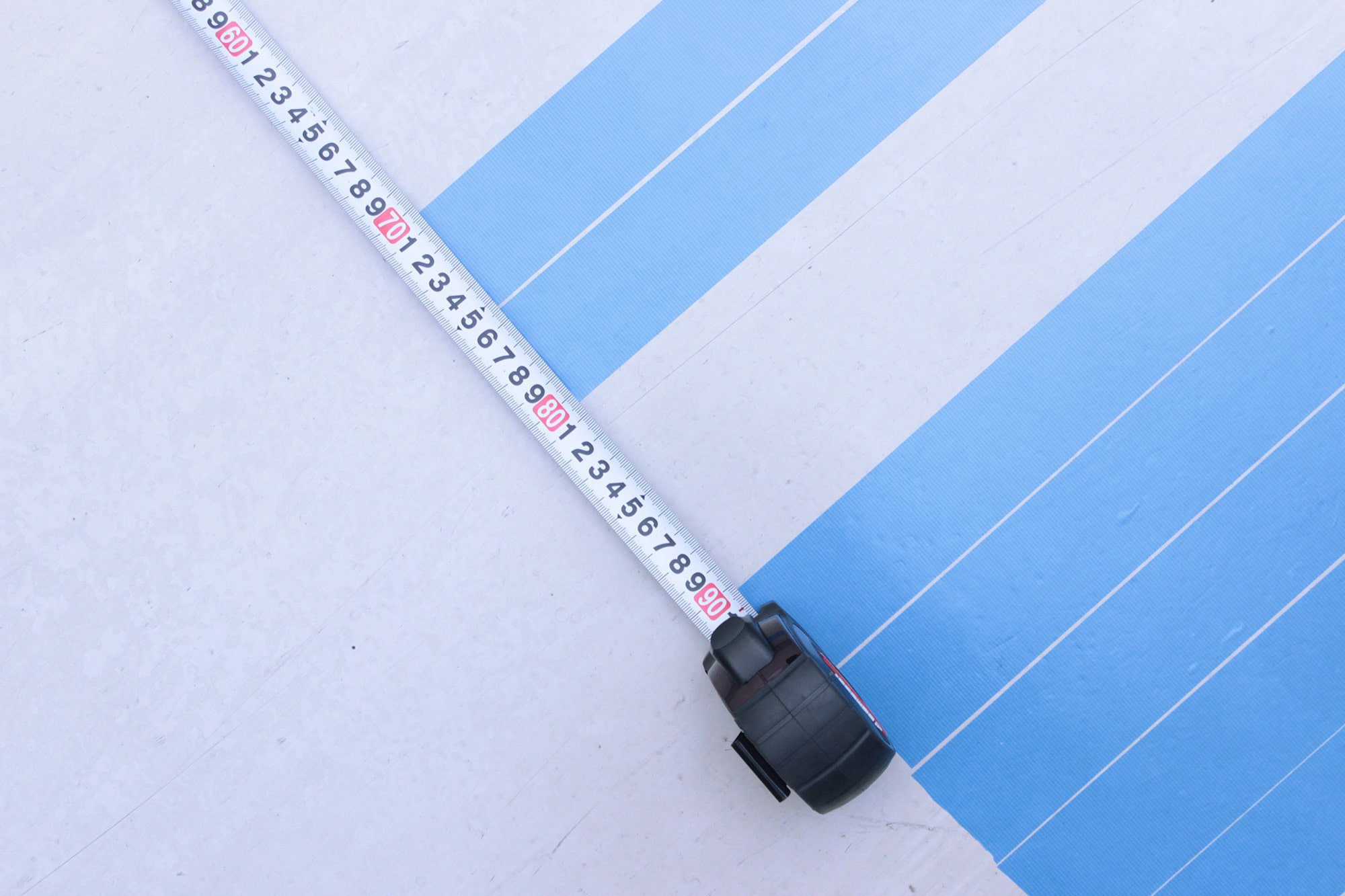2023年度 優秀賞
芸術と生活する
《サン・チャイルド》設置プロセスから考察するアートプロデュースの必要性
- 花島 果椰さん
- 林田ゼミ

📝要旨📝
《サン・チャイルド》は、2011年に東北地方を中心に発生した東日本大震災をきっかけに現代美術作家ヤノベケンジ(1965-)によって制作された立体作品である。全部で3体制作され、2011年11月に大阪の万博記念公園で公開されたのち、日本にとどまらずロシアやイスラエルなど様々な場所で巡回展示されてきた。2018年8月には、福島市にある複合型教育施設「こむこむ館」に恒久設置として置かれた。ところが、設置からしばらく経ち、市民から「当時(7年前)の状況がよみがえる」「像が着ている防護服が風評被害につながる」等の議論がSNSを中心になされた。市が「こむこむ館」で行ったアンケートでは110人が回答し、設置に反対が75人、賛成が22人、その他が13人であった。その後、市が撤去を決め、恒久設置するはずであった像は、わずか48日で館の前から姿を消した。撤去に至った理由について、当時の福島市長は会見で「復興の象徴になりうると期待して設置したが、合意形成のプロセスを欠いてしまった」と発言している。
彫刻作家・彫刻評論家である小田原のどかは、自身の著書『近代を彫刻/超克する』(講談社、2021年)第2章「拒絶される彫刻」の中で本作の福島における事例を、行政によるトップダウンで設置された作品に対して住民が反対し、撤去を求めた公共彫刻の一例として取り上げた。小田原は、著書の中で地域住民との完全で完璧な合意形成は難しいとした上で、「すべての過程を透明にすることは難しくとも、首長の独断的決定によらず、有識者によるレヴューや公の審議を経て、ある程度開かれた検討の場を設けることが必要である」と主張している。ここで、小田原は作品を設置する際の地域住民との合意形成は必要不可欠とした上で、住民との合意形成の仕方について指摘している。では、作品が「恒久的」に人々に受け入れられるには、どのようにして住民と合意形成を築いていくべきなのか。そのような観点において注目すべきが2012年から大阪の阪急南茨木駅前ロータリーに恒久設置されている《サン・チャイルド》である。「こむこむ館」に立った作品と同じ型で作られ、ほぼ同じ時期に制作され、同じような造形を持つ本作は、南茨木という土地で生活の中に溶け込んでいる。本稿の目的は、研究対象である南茨木の《サン・チャイルド》がどのようなプロセスを経て設置に至り、どのように作品と住民の関係を構築したのかについて明らかにすることである。そして、この事例を通して芸術作品を公共の場所に設置する際にはどのようなマネジメント、プロデュースが必要であるかを考察する。
そのためにまず、第一章では作品概要を確認するとともに、作家や制作に携わっていた当時の学生に話を聞き《サン・チャイルド》が作家を含め多くの学生が東日本大震災直後の希望を持つことすらできない状況の中で、希望を照らすモニュメントとして制作されたことを明らかにする。さらに、南茨木に置かれた《サン・チャイルド》の比較対象として、2018年に南茨木駅前と同じ公共の場である福島市の複合型教育施設「こむこむ館」の事例を挙げ、本作品が設置されるまでプロセスを当時の新聞や記事を元に辿り、そこでは地域住民と作品を直接繋ぐような下準備、活動がなされていなかったことを確認する。第二章では《サン・チャイルド》の設置を決定した茨木市と、《サン・チャイルド》を地域に迎え入れるためのプロモーション施策「ようこそ!サン・チャイルドプロジェクト」を行った市民団体「茨木芸術中心」の活動に注目する。当時の担当者であった茨木市役所職員、市民団体のメンバーであった方への取材を通して、これまで明らかにされることのなかった、作家の選定から《サン・チャイルド》の設置までの経緯や活動を丹念に記述していく。そして、そこでは行政の住民に対する細かい配慮や土壌づくり、市民団体の地域住民を巻き込んだイベントや展覧会が行われていたことを示す。第三章では、2012年3月11日に《サン・チャイルド》が地域住民に初めてお披露目された除幕式で何が行われていたのか着目し、当時の担当者の方がインタビューの中で述べていたように地域住民と一緒に作品を設置するという想いのもと、多くの住民が式の運営側として携わったことを明らかにする。終章では、公共の場所という芸術に普段親しみのない人も生活の中で作品に触れざる得ない状況下に、芸術作品が設置される際、茨木市や市民団体が行った「現代美術を受け入れる土壌づくり」「その場所に作品が存在するという妥当性づくり」がマネジメント、プロデュースする側には必要であると結論づける。その上で、2023年度のヤノベプロジェクトに参加し、現在同市でヤノベケンジ《SHIP’S CAT》のプロモーション企画を担当する筆者自身の経験を記述し本稿を結ぶ。