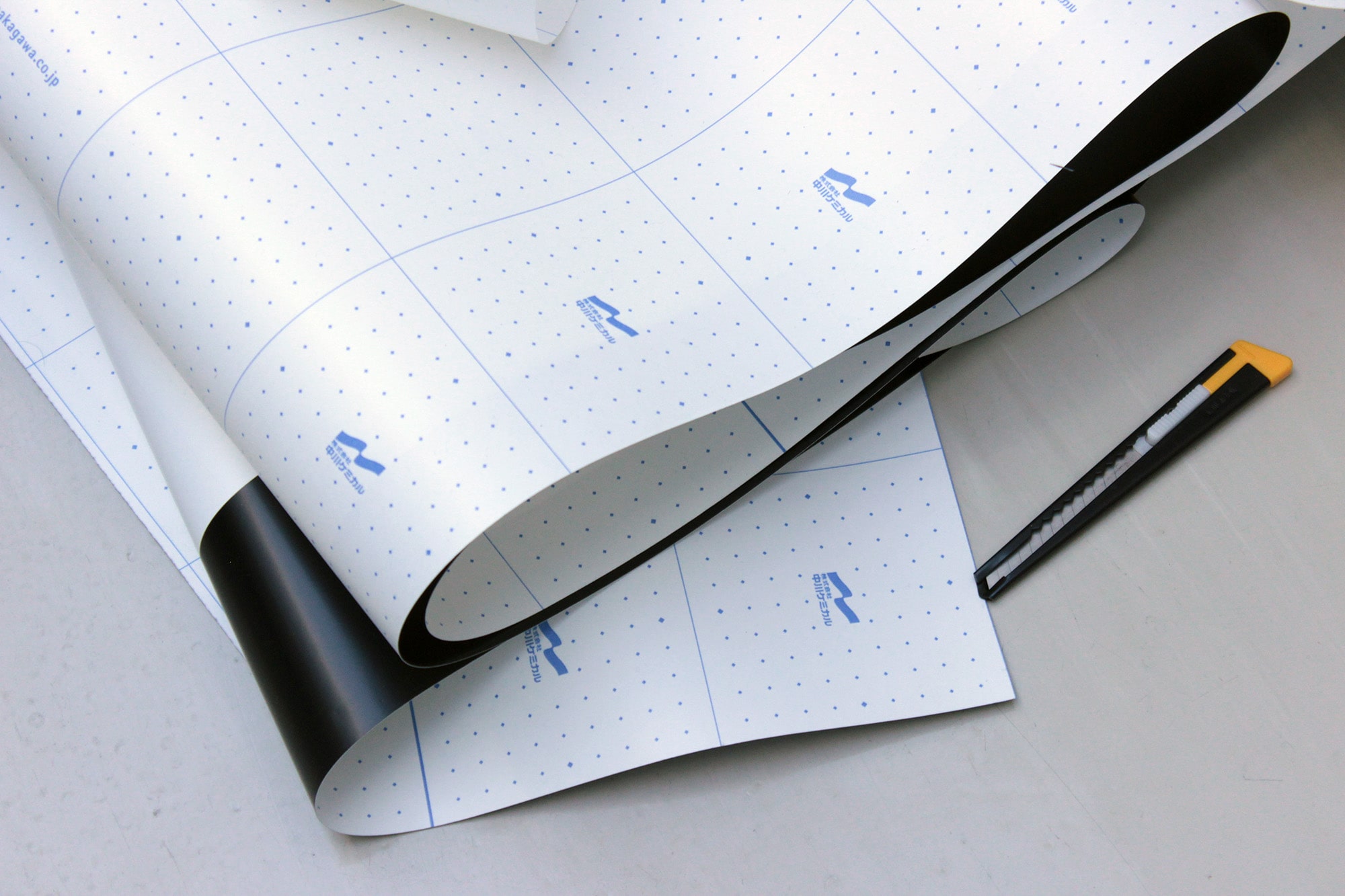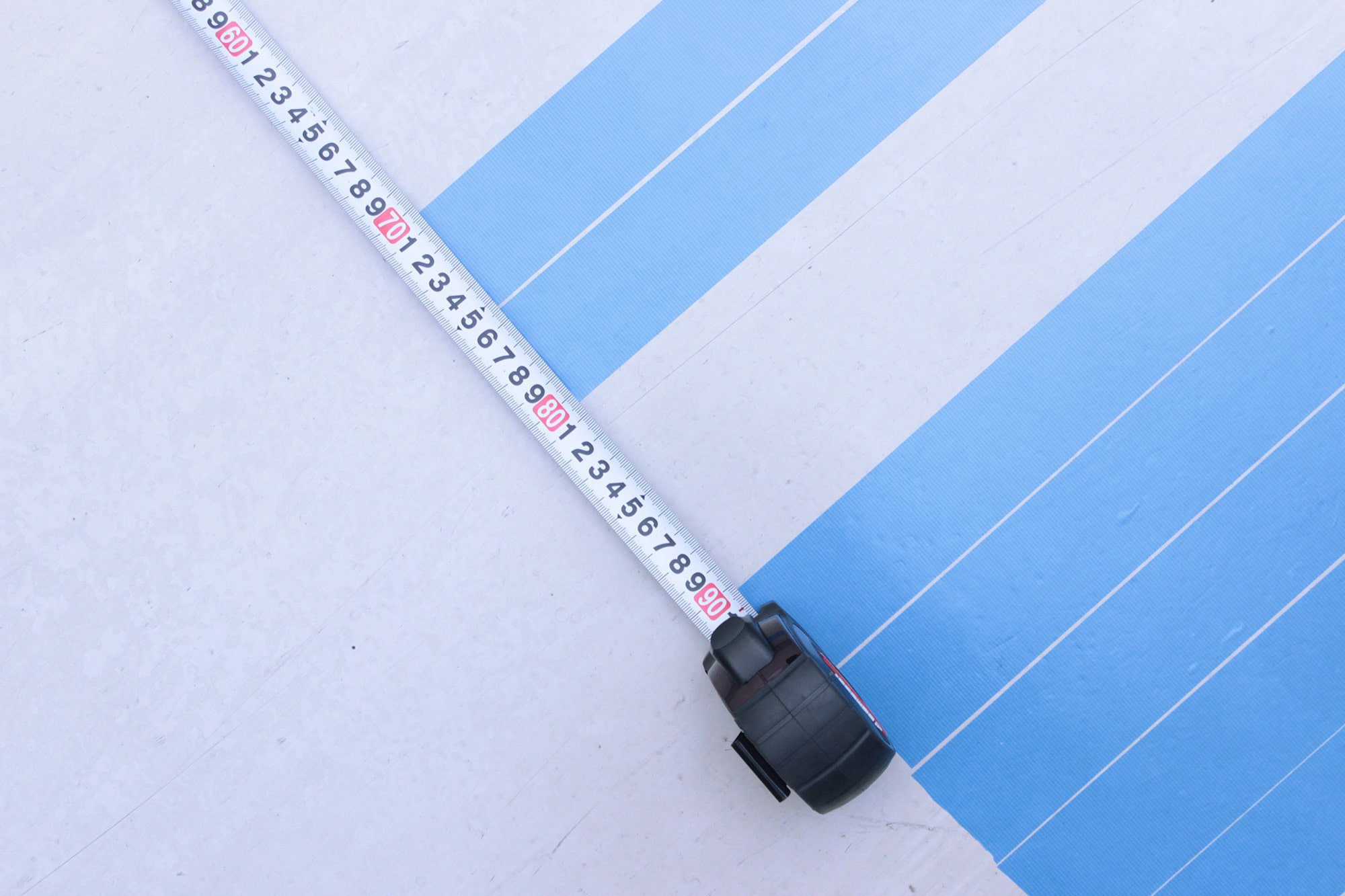2023年度 同窓会特別賞
私から私だけではないものへ
経験をとらえる試み
- 向江 夢さん
- 伊達ゼミ
📝要旨📝
本論文は「インタビューの経験をどのようにとらえることができるのか」という問いが基底にある。本研究の過程で、喫茶玉一という、1920年代から暖簾分けをすることで大阪を中心に店舗を拡大した喫茶店のマスター3名へインタビューを行った。このインタビューは、喫茶店がどのように続けられてきたかなど喫茶店の経営に関する質問だけでなく、マスターのこれまでの人生についても話をきくなどしており、ライフストーリーインタビューに相当するものである。
しかし、そこで語られる、あるいはインタビューの結果として取り出される人生は常に限定的で切り取られたものである。過去の全てを語り尽くすことができないように、どうしても取りこぼされるものが存在してしまう。
この問題を考える視点として、井上俊(1938-)は、人生を物語としてとらえることを提唱する。私たちは、生きているなかで生じる出来事を、理解し、構成して、意味づけることで「人生」としてとらえることができるという。そもそも固定されたまとまりとしてあるわけでなく、出来事を構成し、意味づけることで人生という物語として語っているということである。インタビューの場での語りの場合は、さらに聞き手も語りの意味づけに作用し、その場に応じて構築され語られている。
本稿は人生の物語が、語り手のなかで、そして聞き手との作用のなかで、意味づけ、構成し、語られるという構造を踏まえながらも、分割しえない人の生を扱うインタビューのあり方の可能性を考察した。
第一章では、まず筆者が考える「分割しえなさ」のニュアンスを、作田啓一(1922-2016)の「生成の世界」概念を援用して形容した。作田はアンリ=ルイ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson 1859-1941)を参照し、世界を定着の世界と生成の世界に二分する。科学が対象とするような定着の論理(分割の論理)の世界に対し、生成の世界とは、リズムや感情や運動など分割不可能なものを「メロディやリズムなど記号表現の根底にある論理」によって、暫定的にとらえるにふさわしい世界である。生きるなかでの経験やインタビューの場の経験もまた切れ目のない一つのつながりを持った全体であり、言葉のような定着の論理で切れ目を入れ、分割してしまうと別のものになってしまうのである。
第二章では、こうした切れ目のない経験が、どのように物語化されることになるかを述べる。野矢茂樹(1954-)は、『語りえないものを語る』のなかで「典型的な物語」という用語を用いる。典型的な物語とは、不必要なディテイルや一切の個性を持たない「ふつうの」物語であり、物語のフォーマットとして機能している。しかし、現実は豊かなディテイルをもつため、関心さえ向けられれば「典型的な物語」からはみ出す新たな物語が生まれることになる。
第三章では、聞き手との関係のなかで「語るに値せず語られないこと」について述べる。語りの取捨選択はインタビューの場に限ったことではない。多くの場合私たちは、その場に応じて意識的に、そして無意識的に、語るべき出来事に優先順位をつけ、語り、記述をおこなっている。しかし、典型的でドミナントな物語のなかで語るに値しないと判断されるこれらにこそ、分割しえない経験のディテイルが溢れていると論じた。
第四章では分割しえないものを再現するための参考として、近森高明(1974-)による寺田寅彦(1878-1935)のエッセイ群の批評を取り上げる。近森は、寺田のエッセイがディテイルを詳細に書くことで私の存在をできるだけ廃し、私の個人的な経験を突き抜け、現象そのものを取り出そうとしていることを見出している。私の個人的な物語のディテイルを執拗に語ることで、私の物語ではなくだれのものでもないイメージを帯びたものになることは、私のインタビュー経験を通しての記述ではなく、インタビュー経験において、人は誰しも細かなディテイルを持っているという普遍性を再現しようと試みるものである。
本論文では、インタビューの経験という分割しえないものをとらえるには、個人的な経験を私のなかに閉じ込めず、「語るに値せず語られないこと」を含めて、詳細に語ることで「私のことであり私のものでないこと、誰かのことであり誰のものでもないこと」を書こうとする試みが、現時点で有効であると結論付けた。加えて、本論文でのこれら要素を踏まえ、インタビュー経験の最終的なアウトプットとして「書く」の実践を試みた。