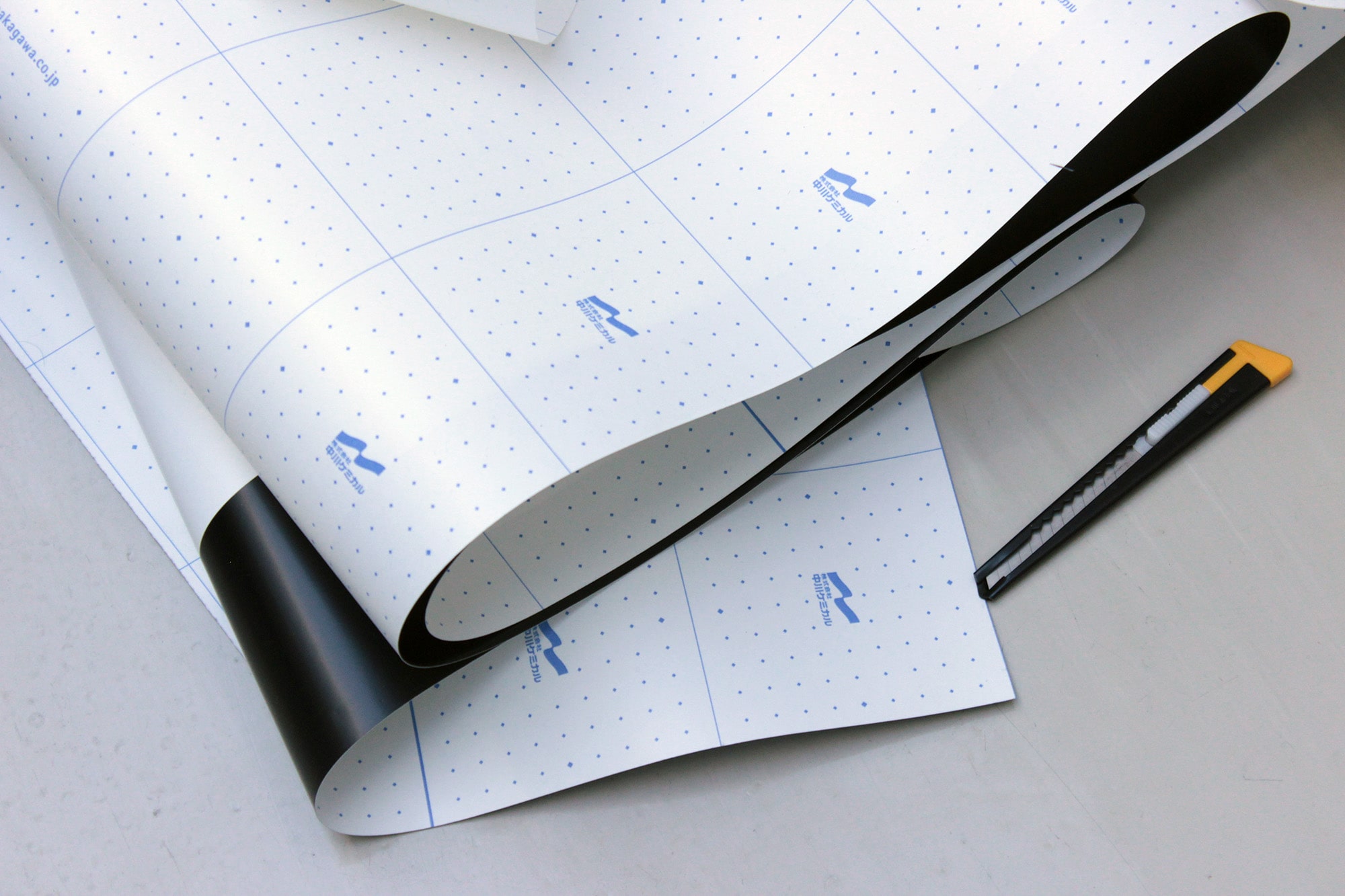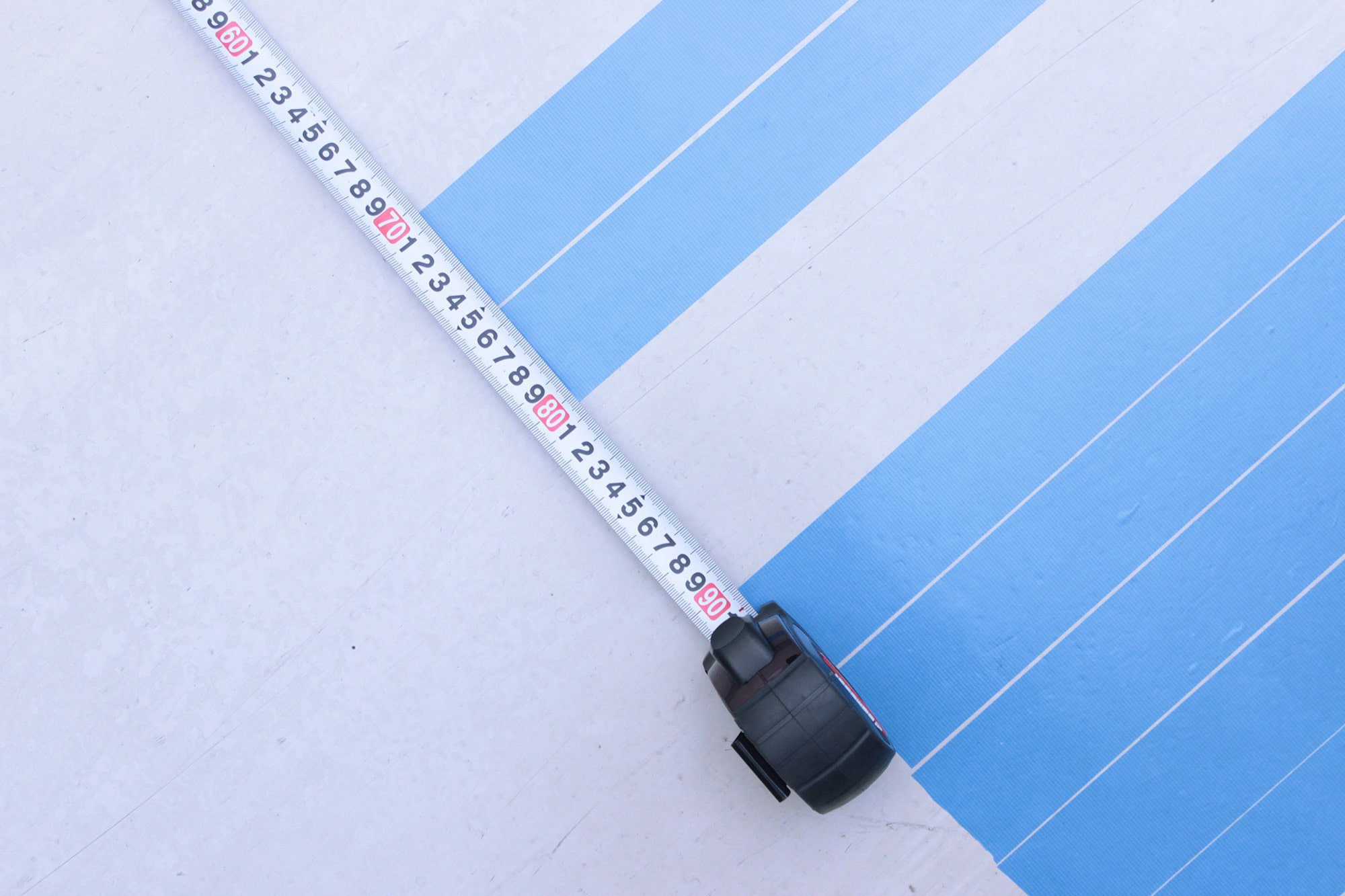2023年度 奨励賞
権威に揺れる身体
自己の縁にみたダンスの限界
- 川崎 彩可さん
- 山城ゼミ
📝要旨📝
1962年、ニューヨークのジャドソン記念教会で興ったポスト・モダンダンスは、バレエや当時権威のある存在となっていたモダンダンスを否定し、「歩く」「走る」「しゃがむ」といった「日常の動き」を用いたことで知られ「見せもの」としてのダンスとはかけ離れた華やかでない、簡素な作風から「前衛ダンス」とも呼ばれる。ダンスの枠組みを広げたポスト・モダンダンスは「なにがダンスなのか」というダンスの「What」の部分を追及し、研究者たちは「なんでもダンスとして見ることができる」という姿勢が重要であると述べ、ダンスを芸術という枠組みの内側に招き入れることによって評価した。
本論は、ジャドソン教会派の理念とその反スペクタクルの実践によって達成されたダンスの大衆化について、その一般的な理解と対向する踊り手の視点に立ち元来ダンスの根本的なミッションである踊る身体と観客の身体とをいかに統合するかという問題こそがバレエやモダンダンスを乗り越える所以とする仮説のもと、「見せもの」としての性格を取り払う方法をとった〈ダンス〉についての論考である。そのため、1962年以降ポスト・モダンダンスを皮切りに始まったダンスと芸術の越境により何か別の芸術形式として現れてきた「ポストモダニズムのダンス」と混合してはならないことを指摘する。ポスト・モダンダンスを創始したジャドソン教会派の第一人者であるイヴォンヌ・レイナー(Yvonne Rainer,1934-)が1965年に創作、そのアイコン的作品である『Trio A』にスポットを当て、ポスト・モダンダンスが問うたとされたダンスの「What」に加え、それが現在のコンテンポラリー・ダンスにおいても参照されるべきという点で踊り手にとって重要などう踊るかというダンスの「How」にも着目する。
踊り手の身体と観客の身体をいかに統合するかという問題は両者の間で起こる出来事にその身体の動きにより能動的に働きかける踊り手側にとって重要な問題であり、ダンスにおける本質的な課題であると考える。よって、これまで語られてきたポスト・モダンダンスに対する価値体系は芸術という枠組みの作用による見立ての問題に解消してしまうとした先行研究に触れ、ジャドソン教会派の理念が踊り手と観客の関係を固定したスペクタクルの制度自体を否定したことであったと確認した上で踊り手の視点の重要性を明らかにする。そのために自己と同化すべき他者から他者へ媒介するためのダンスに欠かせない要素である振付に着目する。『Trio A』は区切りや音にノる要素がないことから即興のようにも見え、また無音でありながら振付が存在する作品である。振付は、それを生み出した自己の身体的な感覚を一度自分の外へ開け放ち、言葉と身体の動きからできるだけ適切に踊り手という他者へ渡す作業である。踊り手にとっては一度外へ放出された他者の身体感覚を自分の中へ取り込み定着させるというプロセスを通して、ダンスを絶対的なものへと昇華させる作業である。踊り手は他者の身体感覚を〈自分のもの〉にしなければならない。そのためダンスから「見せもの」としての性格を削ぎ落とした『Trio A』にとって、レイナーが踊り手にどう踊らせたのかという「How」の問題を追及することは重要であると考える。1978年にレイナー自身が踊った『Trio A』のソロステージ映像を参照すると、そこでは確かにダンスにおけるスペクタクルが拒否されたことが窺える。しかしバレエの型と「日常の動き」の両方を確認することで、踊り手にとって切り離したくも隔絶し切れない権威を見出す。ジャドソン教会派が否定したモダンダンスの権威主義は、〈ダンサー〉によるいかなる身振りもダンスになり得るのだ、という形でまた新たな権威として蘇ってくるのである。また実際に『Trio A』のショーイングに出演した日本人ダンサーの言葉と資料より、観客を見ないこと、身体を誇示して「魅せる」ことはしないなどは、オリジナルから守られる『Trio A』のルールで、レイナーらが考案したのは観客が見て取れるのと同じエネルギーで踊るというダンスの「How」であった。
ジャドソン教会派による反スペクタクルの姿勢は「何でもダンスとして見ることができる」ことを達成させたと見立てられてきたが、踊り手にとっては観客という他者に、自分という他者と向き合うことに、ダンスとして妥協しない挑戦だったのだ。そこでは踊り手の単なる「見せもの」ではない、いかに同じ身体として魂を震わせられるかという熱望を、ダンスにとって重要なことを忘れてはならない。レイナーのあえて「スタイル」を取り払うという方法は観客に共有可能な「日常の動き」として表出され、見ることの困難を自覚させた。しかしそれよりもダンスを自分のものにすることの困難を確認するのだ。またそれを観客のものとすることの不可能性を自覚した踊り手が今もなおその身体を誇示し続けるための参照項であったのではないかとの考察を持って結論とする。
レイナーは言った。「ダンスとは本質的に「私(Me)」にかかわるものなのだ。」「私」とは、誰でもなり得る踊り手自身のことだ。踊る自己自身に向ける客観的な視線が備わったダンサーたちは自己という他者の際どい縁で観客と繋がることを熱望した最後、ダンスの限界点に直面したが、自己の身体を誇示し続けるために、ダンスを万人のものにするような見かけを呈したポスト・モダンダンスを経て〈コンテンポラリー〉に踊り続ける。