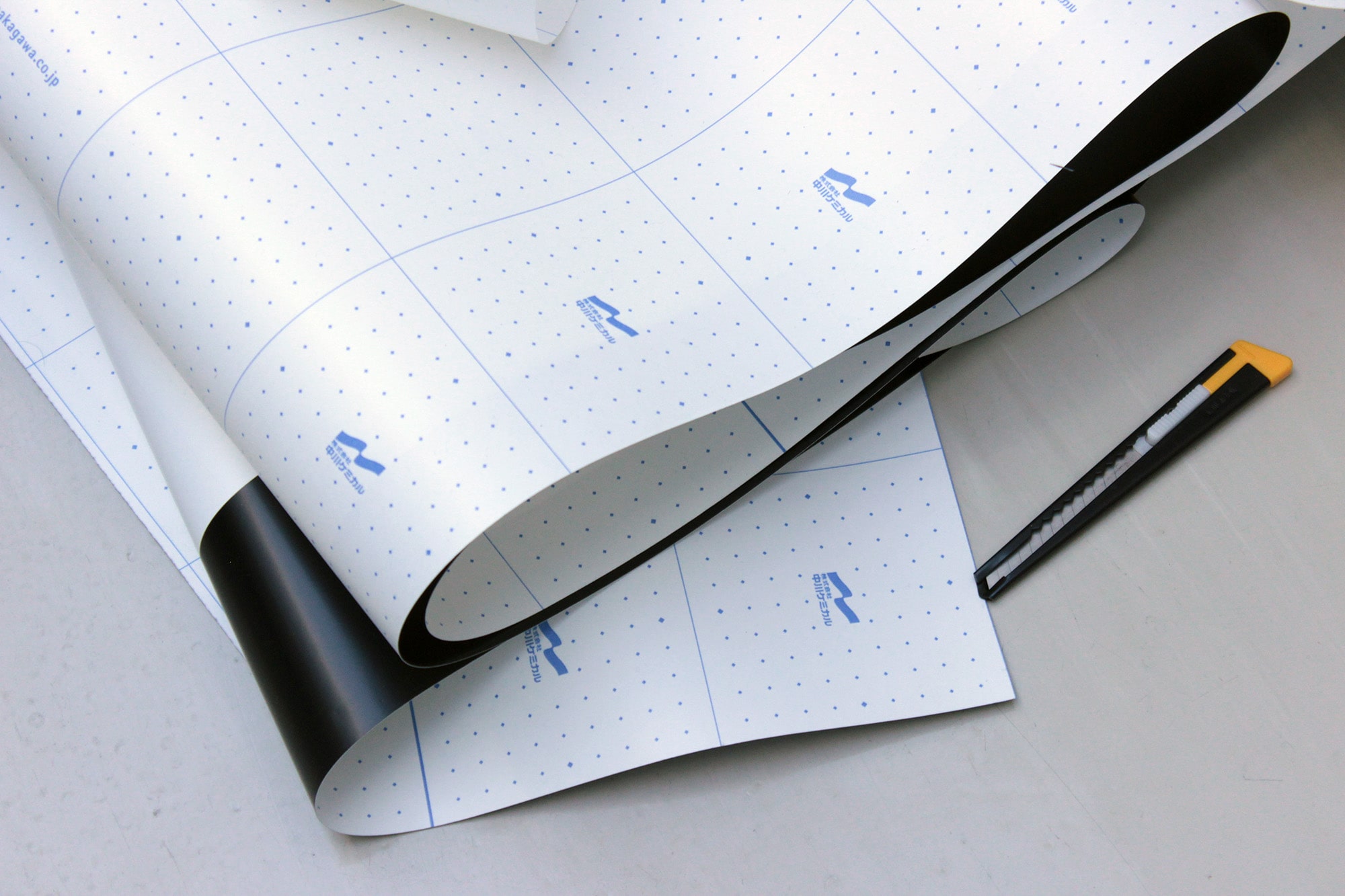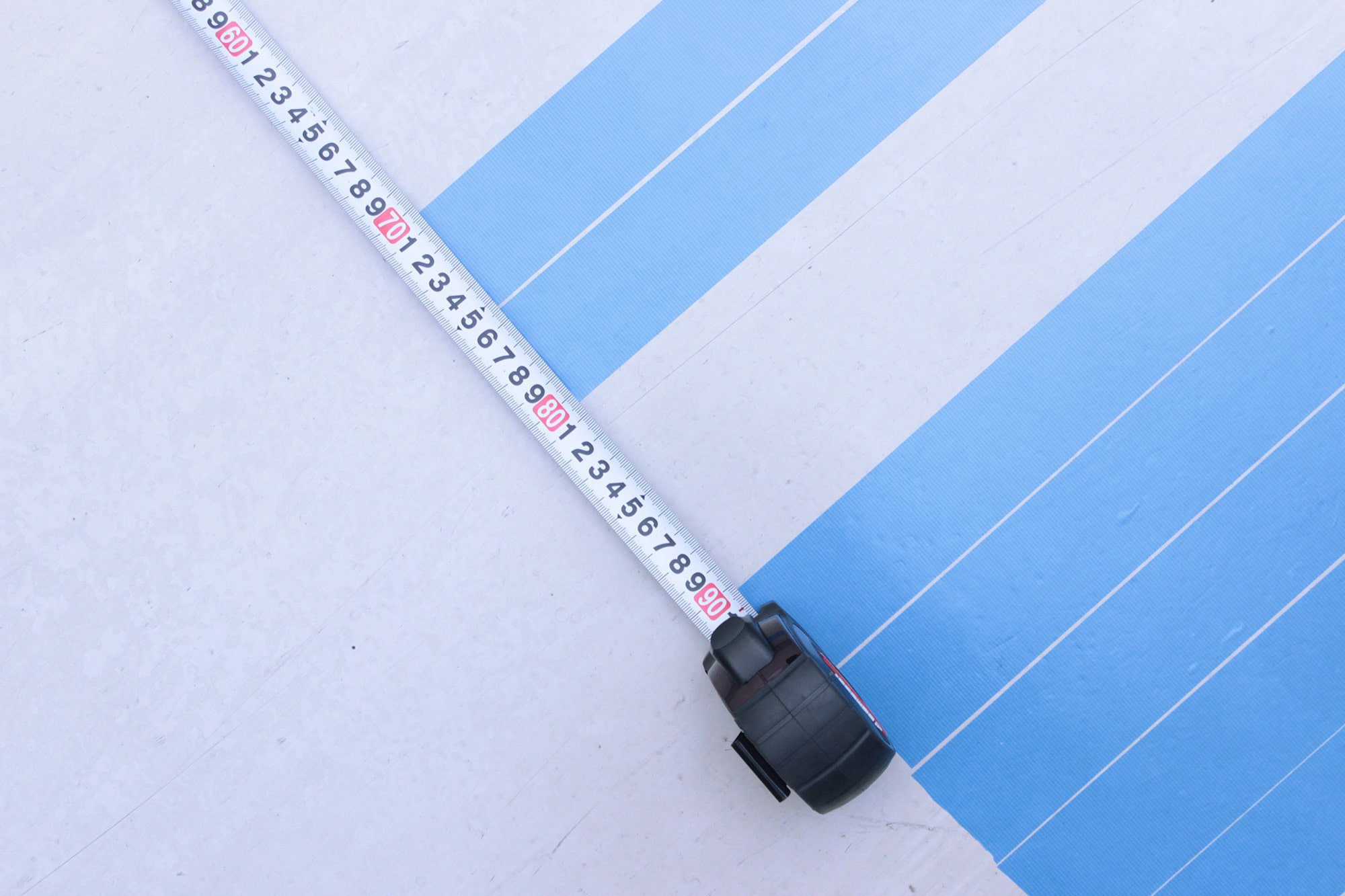2021年度 学長賞
裂かれた経路内奥で生じる“詩”
──詩作品《破帖》(1937年)の翻訳と読みとき──
- 毛利風香さん
- 林田ゼミ
📝要旨📝
《破帖》(1937年)は、作家の死後、1937年創刊の雑誌『子午線』(子午線社、1937年)第一号に掲載された詩作品である。作家(이상,1910-1937)は1910年朝鮮に生を享けた。当時としては充実した教育課程を修了したのち、朝鮮総督府に勤務しながら1930年代初頭より筆を執った。生前、作品の傍に賞賛が寄せられることは極めて少なく、その晦渋な作風から難解さや意味不明さばかりが取り上げられたが、朝鮮総督府退職後も継続して作品を書き連ねた。1936年に来日した東京でも執筆活動を一層精力的に行うものの、1937年、東京・神田で思想犯の嫌疑を受け、拘禁された。その後、持病である結核の悪化により客死した。
李箱作品の再検討は1960年代頃から始まり、1990年以降はテクスト分析の傾向を強めながら、多様化してきた。ところがそれらの研究は李箱のテクストが日本植民地下で執筆、発表されたことを鑑み、〈作品―作者―社会〉の相関関係のうちにテクストを読むことに注力してきた。しかし本論ではこうした立場はとらない。
ロラン・バルト(Roland Barthes,1915-1980)は『物語の構造分析』(花輪光訳、みすず書房、1979年)において、経験主義や合理主義、宗教改革を経て個人的信仰へ向かう中で個人の威信、つまり「人格」の威信が発見されたことが、作者の登場に繋がったと分析する。すなわち威信のある「作者」とは歴史的に形成されたものにすぎず、それは「単に書いている者であって、決してそれ以上のものではな」い。
これまで李箱作品に指摘されてきた晦渋さもまた、作者ではなくテクスト上にこそ棲みついている。そうであるならば、テクストが書かれたときすでに切り離されたところで独立する作者をはじめとする作品の外在的来歴に結びつけるよりも、テクストを一字一句ほどくように読むことによってこそ晦渋さを乗り越え、《破帖》を “詩”たらしめるものに接近することができるのではないだろうか。
本稿ではこうした立場に立ち、《破帖》というテクストを忠実に読みすすめることを試みる。本作に潜む不可解さや意味不明さはそのままに、内容、記号、改行に渡るまでを文字通り読みといていく。“文字通りに読みとく”とは、〈文章―語―記号〉に渡るまでを読みとくことで、歴史の反映とみなされるものあるいは作家性の表出とみなされうるもの、そうした外殻を突き破りその内奥へと深く潜り、言葉が生まれるまえのような、あの言葉を授けようもないような原初的な空間へ向かうことである。言い換えれば、衝突する謎めいた事柄をすべて引き受け続けるテクストの読み方を以って《破帖》における“詩”へと迫ること、それが本稿の目的である。本稿の記述は、従来の先行研究と比較した場合、些か共有し難いものへ向かうかもしれない。しかし《破帖》というテクストには表出し得なかった諸現象を経験し、それらを文字で記述するという共有困難さのうちに於いてこそ、“詩”に迫ることができるのではないだろうか。
本稿では、テクストを読みとく支度として《破帖》テクスト資料の再検討・再作成を行なった。ハングル版テクスト資料は、『韓国詩雑誌全集』4巻(韓国文化開発社、1974年)、『증보 정본 이상문학전집1_시(増補正本李箱文学全集1_詩)』(소명출판、2009年)それぞれに掲載される《破帖》のテクストを参照し、筆者はあらためてハングル版のテクスト資料を再作成した。日本語版資料は、再作成したテクスト資料の筆者による邦訳からなる。尚、テクストの読みときは、《破帖》に記される1-10までの数字に即してすすめる。それらを基に本稿では以下のような手続きをとる。
第1章では、李箱文学にまつわる先行研究の多くが、作家論や社会論を補強するようなテクスト分析に終着する傾向を指摘したのち、本稿ではそれらとは異なる“テクストを文字通り読みとく”ための立場を建設する。ひいては、テクスト、それを媒介に存在するとみなされる作家と語り手の関係を本稿ではいかに思考するかを記述し、《破帖》のテクストを読みとくための支度をする。第2章では《破帖》を読みといていく。まず数字1-6に、数字と各テクストの関連性を観察しながら、物語のない断片的なテクストとして読む。また、語り手が市街地やこの世の何処かも知れぬ空間を渡り歩く様を精細に追うことで、テクスト内に拡がる諸現象を機に、テクストを媒介に語る彼の存在が揺らぎはじめることを明らかにする。続く第3章では、数字7-10のテクストに、何処でもないような空間を彷徨う語り手が、やがて亡失していく様を追行する。他方、前章までの読みときを元に、語中間の改行などを起因に内部損傷がテクストに生じること、そして数字1、10に書かれた語「門」は、同一性を有した異なる「門」であり、そこがエクリチュールの周期地点であり差異の発生地点であると確かめる。このようなテクスト内外の損傷が延々とずれた反復を起こすことでひらくテクストの裂け目、その内奥にこそ“詩”は発症する。これを《破帖》における“詩”と結論付ける。結びでは、筆者の経験を手がかりに《破帖》初出までの経路を辿ることで、本作がテクストの不確実性それ故に翻訳不可能性を保有することを記述する。またその不可能性に内包されてこそ“詩”はひらかれるが、“詩”とは、たとえ読む者が不在であっても尚そこで生じる、それは同時に、時空間を超えた他者へと宛てた可能性のあらわれである、として本稿を結ぶ。