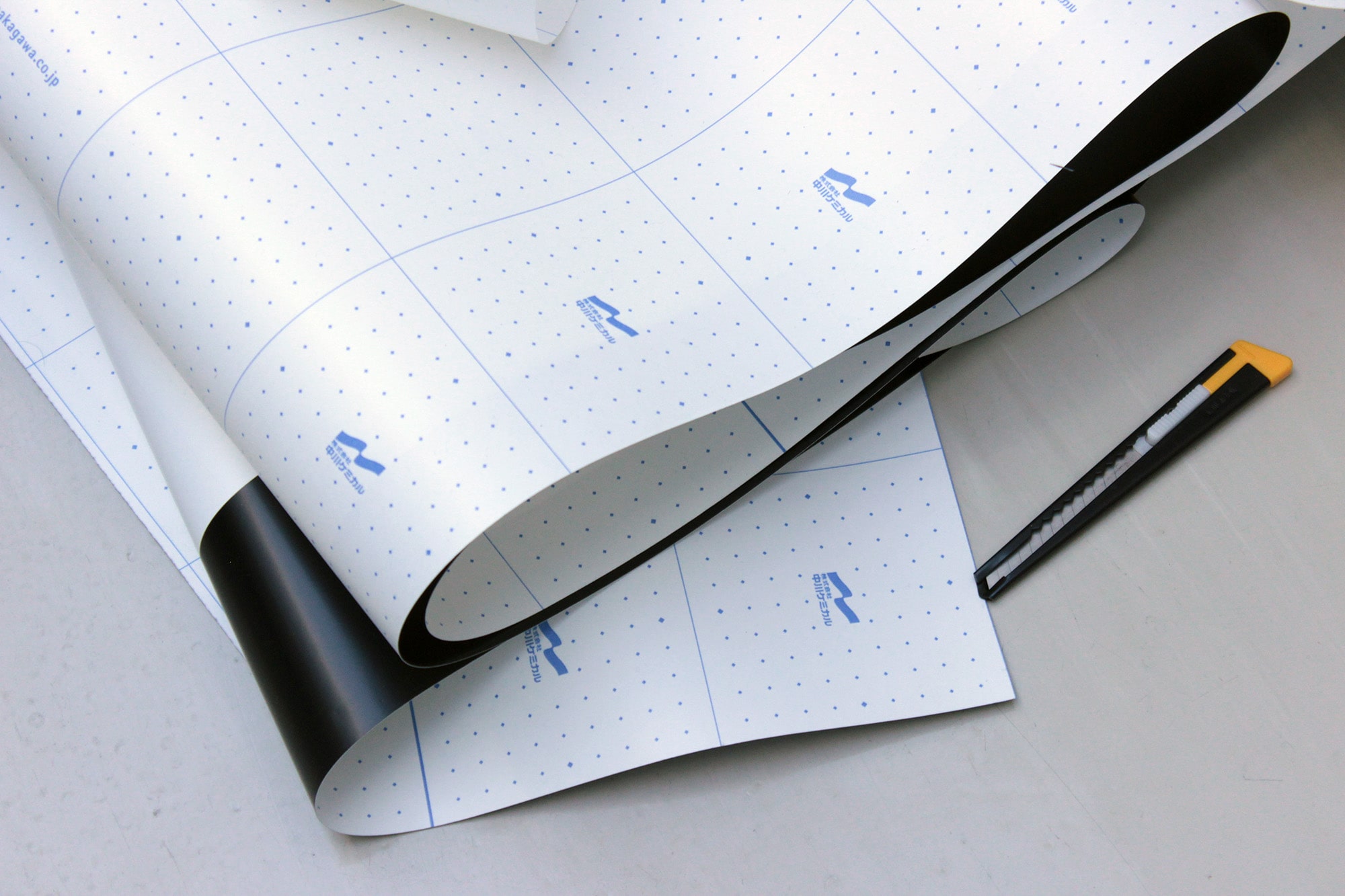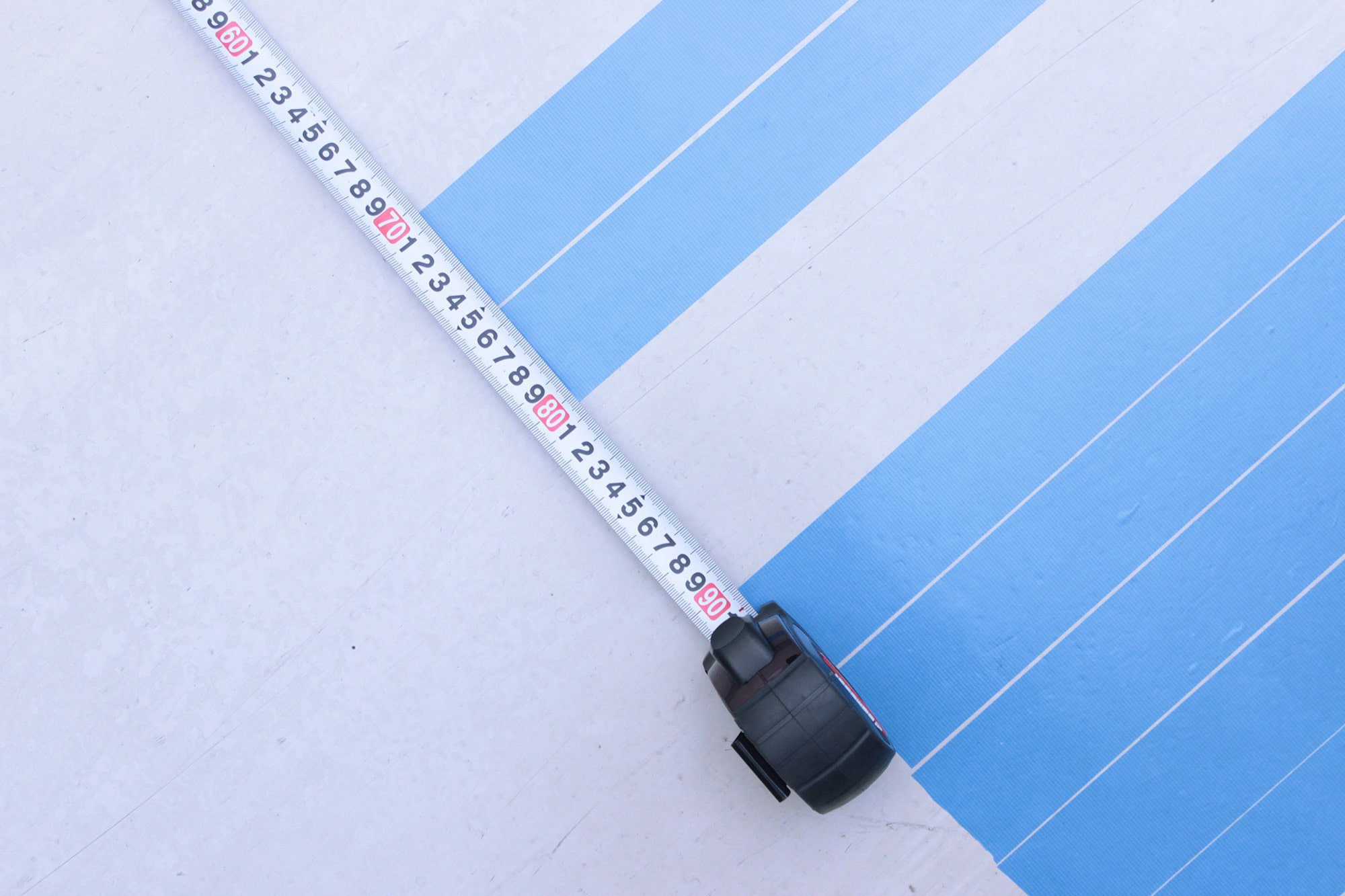2018年度 学長賞
衣服における「第二の皮膚」概念の系譜とその更新のあり方
──ISSEY MIYAKE《Tattoo Body》から《A-POC》、そしてSOMARTA《Skin》へ──
- 川名 佑実さん
📝要旨📝
日本における衣服批評は―試み自体は点在し始めているとは言え―それが盛んであると断言される程には未だ試みられていない。批評媒体の母数が少ないことにも影響を受けてか、批評に関しての共通言語も非常に限られている。そうした状況の中、1980年代から1990年代にかけて一時的に衣服批評が隆盛する状況が見られたが、そこでは我々の身体表面の最も近くにある衣服とは「第二の皮膚」であるとして、それがしばしば有力な批評言語として用いられてきた。
かつて批評家のH.M.マクルーハン(Herbert Marshall McLuhan,1911-1980)は『メディア論―人間の拡張の諸相』(1964)において、全ての発明或いは技術、そしてその産物たるメディアは我々の身体及びその感覚を拡張したものであると主張した。そうした主張の中では、更に「衣服」もまたメディアの一種と捉えられており、その最も近くにある人間の皮膚に着目して、衣服は「皮膚の拡張」であり「身体の外表面をより直接に拡張するもの」であると述べられている。こうしたマクルーハンの言説に端緒をなし、批評の場において衣服が人間の身体に次ぐ「第二の皮膚」として語られ始めることとなる。
この「第二の皮膚」概念に対しては、哲学者の鷲田清一(1949-)が度々自身の衣服論においてその理論の一部を踏襲しつつ、その脱臼を試み、衣服と身体との関係性を問い直していった。例えば鷲田は、今日まで日本の衣服製作を牽引してきたデザイン企業集団イッセイミヤケのデザイナーの三宅一生(1938-)が手掛けた《Tattoo Body》(1970,1989)について、この衣服は、衣服が第二の皮膚であるというよりもむしろ皮膚が第二の衣服なのではないかということを問題として提起しており、我々の存在そのものと衣服を纏うこと自体を問うものであると評している。このように、「第二の皮膚」概念及びそれに関する言及は衣服製作の現場と連動し、一時隆盛した(第1章)。
ところで、2000年代に突入し約20年が経過しようとしている現在、こうした「第二の皮膚」概念における言説とは現在の衣服製作においても有効であり、依然として定義内容に変化はないのだろうか。或いは、概念の名称自体は現在もなお使われていても、既にそこに更新の兆しが見られるのだろうか。変化があるとすれば、それは今日の衣服製作において一体どのように更新されているのだろうか。
本稿ではその変化の程度を解明するべく、「第二の皮膚」概念についての主要言説が提示された後、更に1990年代に入り《Tattoo Body》以降に登場した、身体表面への密着度の高い―つまり皮膚に最も近い衣服の一つとして―イッセイミヤケの無縫製ニットのボディウェア《A-POC》(1999)と、2000年代に入り「第二の皮膚」概念を参照した衣服として登場した、1998年からイッセイミヤケに8年間勤めたデザイナーの廣川玉枝(1976-)がそこから独立する形で2006年に立ち上げたデザイン企業集団ソマルタのボディウェア《Skin》(2006-)をその観察対象として取り扱った。
《A-POC》は先行研究において、鷲田による衣服論を基に、継ぎ目のない統一された全体的な身体像を我々にもたらすような衣服であると論じられている。しかしながら衣服そのものを再び具に観察してみると、そこには部分的にではあるが衣服の下の肌がちらちらと覗くような「編み目」の存在も認められる。それは、鷲田が取り上げていた―目の詰まった、我々の身体に馴染みのある任意の「肌色」の―「人間の皮膚」を再現した《Tattoo body》と比較すると、着用する身体への密着度及び身体の輪郭の再現度は上がっている一方で、それらは赤や緑といった鮮やかな色彩を放ち、編み目という「孔」の生じた、人間の皮膚からやや隔たったデザインとも考えられる(第2章)。
一方《Skin》は、《A-POC》における無縫製ニットの基本的な製作技法を受け継ぎつつ、更にその製作過程で生じる大きな「編み目」を部分的にではなく衣服全体に増殖させるように配置している。これにより伸縮性が向上するため、衣服の中に付属の衣服パーツを入れて着用することができる。骨組み状の肩パッドやスカートのような衣服パーツを装着し《Skin》を着用すると、まるで人間の身体を骨格から引き直したキメラのような輪郭が現れる。また、ニットの編み方を変奏することで《A-POC》に比べ、布地により複雑で多様な模様を生み出すことにも成功している。模様のモチーフは植物や動物、人間の肉眼で確認できない細胞のような小宇宙的な事物など、人間以外の生物や世界が主題となっている。更にそれらは、肩や胸や背中といった着用する身体の各部位の形に自然に馴染むよう、一つずつ微妙に形を変更するデザインを加えられ全身に配置される。加えて、その編み目を組成した模様の上からは、鉱物や金属や和紙を素材とした緻密な装飾が刺繍されており、その様子はまるでそうした物質と人間の身体とが一体化したり、それらが皮膚表面に結露したかのようである(第3章)。
こうしたソマルタ独自の製作を観察すると、《Skin》は「第二の皮膚」概念を参照しつつ、かつての言説のように人間の身体像を構築し再現するだけでも、《A-POC》において確認できた、衣服における「人間の身体の再現」からの離反に止まるだけでもなく、むしろ衣服を「人間の身体そのものを皮膚の間近で引き直し作り変えるもの」として表象しようと試みていることが伺える。
またその着用感覚においては、身体がそこに存在することを経験的に知覚するような引きつりや粘つきといった皮膚感覚が通常の衣服に比べると認めにくいような所が確認できた。よく鷲田の衣服論では、衣服の着用による皮膚表面での経験が我々の身体像の構築に影響すると論じられるが、《Skin》はその着用感覚において、身体の輪郭を際立たせるような視覚的特徴とは相反し、衣服による身体像の構築を目的としていないようにも考えられる(第4章)。
衣服における批評言語「第二の皮膚」についての言説を整理し、イッセイミヤケ《Tattoo Body》に《A-POC》そしてソマルタ《Skin》を観察することを通して、本稿では衣服製作における「第二の皮膚」概念の捉え方が、衣服によって人間の身体を再現するものから、身体そのものを非人間的なものへと作り変えたり、部分的に身体感覚を消失させてゆくような表現へと変遷しつつあることを明らかにした(第5章)。